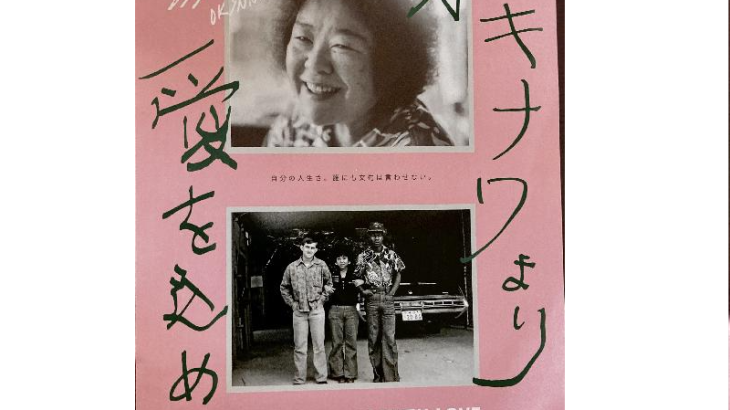長澤淑夫
はじめに
2022年度から従来の日本史と世界史を融合させ18世紀後半から現代までを扱う新教科「歴史総合」(2単位)が始まった。文科省は「近現代の歴史の変化に関わる諸事象について、世界とその中における日本を広く相互的な視点から捉え、資料を活用しながら歴史の学び方を修得し、現代的な課題の形成に関わる近現代の歴史を考察、構想する科目」(「高等学校学習指導要領」2018年)とその目標を記述している。これをめぐり岩波新書で三巻本の『シリーズ歴史総合を学ぶ』が刊行され、これまた岩波の雑誌『思想』(2023年4月号)が高校世界史教育を特集するなど、この新科目は教育界だけに留まらない社会の注目を集めている。そこで今回はこのシリーズの最初に刊行された小川幸司・成田龍一編『世界史の考え方』(岩波新書、2022年)の一部を紹介する。

新教科が望むことは歴史の知識を身につけそれ武器に現実の物事に対処していくのではなく、「ある『問い』にもとづいて歴史の事実をいかに多角的に検討して見いだすかや、同じく『問い』にもとづいて歴史の解釈をいかに事実に即して合理的に導き出すかなどを探求するような歴史学習」であるという。そこで本書では「これまでの歴史学が、どのような『問い』をもって事実や歴史解釈を導きだし、その「問い」の変化によって、焦点となる事実と歴史解釈、そして歴史叙述の方法(作法)をどのように刷新してきたのかを鳥瞰的に考察します」(「はじめに」)としている。具体的には世界史教育者である小川と日本近現代史研究者である成田が、5人の歴史研究者をゲストに迎え、それぞれ三冊の歴史書について「問い」と歴史実践のありようをめぐって対話する形をとっている。なかなか本格的で重厚な試みといってよいかと思う。
「Ⅰ近代化の歴史像」は「第1章 近世から近代への移行」と「第2章 近代の構造・近代の展開」からなるが、本稿では1章を紹介し、コメントしていく。
大塚久雄の発展段階論と川北稔のシステム論
最初に取り上げられたのは大塚久雄『社会科学の方法(岩波新書、1966年)』である。マックス・ヴェーバーに依拠しながら、資本主義の発生史(『欧州経済史序説』(1938年)「これ自体が時代への抵抗を秘めた経済史」と小川は解釈)に、それを可能にした人間の生き方はどのようなものであったかという『「問い」を接ぎ木し」たところに大塚の独自性があったと小川は把握している。1大塚は、著書でロビンソン・クルーソーという理念型を示し、合理的、禁欲的に経済活動を展開する人間たちが「近代」を生み出したと考え、欲望の解放、消費が「近代」を形成したとする研究を否定しているという。とはいえ資本主義の暗い面に自覚的だった大塚は、スウィフト『ガリヴァー旅行記』のヤフーの国をあげていることを指摘し、成田のコメントに移る。成田は「ありていに言えば、帝国主義をめぐる認識を大塚は持ち合わせていない」とし、さらに四点、批判するがこれは省略する。
続いて川北稔の『砂糖の世界史』を取り上げ、以下のように小川は紹介している。イギリス資本主義の成立には、大西洋三角貿易による西インド諸島における奴隷労働が大きく関わっているとしたエリック・ウィリアムズの世界史像やウォーラーステインの世界システム論に学びながら帝国支配としての近代イギリスの歴史を探究した。「カリブ海にいろいろな産業が成立しなかったのは、黒人が怠け者だったからではありません」と大塚批判をしつつ世界の構造的不平等に対峙できる歴史学を構想すべきと考える川北の問題意識がここにうかがわれる。さらに世界商品としての砂糖、綿織物、紅茶の消費がイギリス社会を変えたこと、「工場制度とプランテーションはイギリスが中心となりはじめた近代世界システムが生み出した双生児」(『イギリスの歴史』有斐閣、2000年)を小川は引用し、最後のまとめとして「こうして砂糖という世界商品が歴史に与えた明暗の影響が、工業の発展というプラスの面と第三世界の貧困というマイナスの面という形でいまだに世界に後遺症を残しているー川北はそう本書を結んでいます。欲望と消費が資本主義経済を生み出し、欧米の経済発展が低開発の国・地域を構造的に作り出していく。豊かさとか自由といったヨーロッパの『近代』が生み出した諸価値は、自国中心主義の大きな限界をもっているのでした。」と紹介を終えている。
続いて成田のコメント。イギリスの生活スタイルの変化と砂糖、紅茶の消費による「国民化」を描き、生活革命という社会史的論点を加味することで、イギリス帝国の具体相をマクロとミクロの両面から描いたと肯定的に紹介している。
続いて「2 中国史(岸本美緒)から見ると」では中国近世史の研究者岸本が大塚、川北の問いと研究へコメントしていく。大塚の問題意識のうち、農村工業などは中国史でも論じられてきたが、目標として市民社会論は議論されなかったという。それは1949年に中国が社会主義国になっていたためだという。局地的市場圏から中産層が生まれ、その両極分解から資本家と労働者が生まれるなどの議論は今では実証的に妥当しないと考えられているだろうが、モデルとしては立体的で面白いと思っていたという。ヴェーバーのいう合理主義や禁欲といった世俗道徳、奢侈と経済発展の関係などは中国史でも論じられてきたという。
川北本について岸本は「消費生活についての研究は明清を中心に」最近は多い。システム論の影響は受けてきたが、ウォーラーステインの世界システム論はヨーロッパ中心主義と批判するフランクなどは、中国が銀を輸入し、茶、陶磁器を大量に輸出していたので中国がシステムの中心だったと論じているが、こうした構造をあまり固く考えすぎない柔軟な見方が必要とコメントし、社会史についてはヨーロッパと中国は構造がかなり違うので議論にのれないところがあった、と結んでいる。
岸本美緒の「近世」をめぐって
「3 岸本美緒との対話」 ここでは「近世」の新しい歴史像を提示した岸本の『東アジアの「近世」』(世界史リブレット、山川出版、1998年)を小川が紹介する。東アジアが「激動のリズム」を共有してきたから16世紀から18世紀を「近世」として捉えることができると解釈し、具体的には16世紀の急激な商品経済の活発化と社会の流動化の中で旧来の秩序が崩壊して、17世紀から18世紀にかけて徳川政権や清朝政権などの新しい伝統秩序が形成されてきたと岸本はまとめている。より広い視野で見れば、ヨーロッパの絶対主義の成立にも共通する事情ではないかという見通しを展開する。さらに岸本は銀を通して、世界経済の中に東アジアを位置づけ、生糸、ニンジンで新興勢力(例えば清朝を形成した満州族)の性格を分析し、火器を通して覇権争いの動向をたどり、タバコと甘藷を通して近世における地方の人びとの特徴を描いた。さらに小川は、「前近代を旧体制として否定的にみられがちであった伝統社会が、それ自体、歴史のある時期に形成されてきたものであり、その後の歴史に複雑な影響を与えているという見通しを得られるようになりました。」「岸本さんのような視座に立つならば、ヨーロッパ中心史観に陥ることを避けられそうです」と肯定的に評価している。
続く成田は、日本史研究者が後期封建制として「近世」を捉え、それに対してヨーロッパ研究者は初期近代と捉えてきた。日本史研究では「近世」との断絶が近代となるが、岸本さんは東アジア近世を独特の一つの世界と把握しまとめ上げている、とコメントした。
再び小川の発言。教科「歴史総合」で学ぶ「近代」は、それ以前の「近世」の中に胚胎してきたものであり、その制度・規範・社会経済の特徴には、それぞれの社会に固有の価値と多様な課題が内在することや、ヨーロッパの覇権が必然的な展開ではないことに留意したいとし、岸本対話に進んで行く。
対話は二人の質問に岸本が答えるスタイルで進んで行く。執筆時の意図を問われ、岸本は発展段階論の硬さを克服したかったという。つまり「中世は封建制」とすると東京の学会は宋代説を唱えると言った議論を克服するため、16-18世紀という同時代を、内容規定をあえてせずに「近世」と括ったという。世界システム論では「周辺」は自動的に巻き込まれていくという形になりがちなので、「そうでなくて、世界的な交易発展の衝撃に対しても、それぞれの地域がどうやって個性的にレスポンスするのか、といった形で考えてみたら、世界システム論の硬さも少し柔らかく」できると思った、と答えている。私もこの岸本の議論は妥当だと思う。
議論はこの衝撃に日本、朝鮮、中国がなぜちがうレスポンスをするのか、に向かう。以下は岸本の議論:一つの答えはもともとの社会の有り様の違いに求めるもので、伝統社会を流動性の低い固い日本タイプと柔らかい中国タイプに分類できる。朝鮮は中間。二つ目は清を建国した女真族のあり方に注目する答え。諸民族が入り交じる辺境から商業的な現実感覚を発揮しつつ、のし上がってきて、銀の衝撃にうまく対応しながら女真族は新国家を建設し、海外貿易をうまく行う体制を作った。日本の織豊政権も商業を重視していたが、銀を輸出し、商品を買う「後進国」的な構造から、徳川政権になるとポルトガルへの脅威を感じて、倭寇を抑えつつ「鎖国」へ至り、輸入代替的な産業を発展させる道を選択したと理解できる。この内需主導型が近代以降は有利に働いたと思う。他方清朝は、いわば自由な倭寇的勢力が国家をつくったとみることができる。
続いて、前近代の中国は個人の自由競争的な社会で、社会集団があまり意味を持たないが、清朝は社会政策的な介入は行っていたことなどを岸本がヨーロッパとの比較を交え説明し、この節は終了する。
まとめ
最後に、この章を小川がまとめと「歴史総合」の授業で考えたい「歴史への問い」が列挙されている。一つだけ例をあげておく(残りは注を参照のこと)。[2]①「イギリス・フランス・アメリカが歴史発展のモデルである」という歴史の見方はどのような点をその根拠としているのだろうか。またそうした見方の問題点は、どこにあるのだろうか。
「問い」を自ら考え、「答え」を資料と討論によって考察する、何か理想的な感じがするとはいえ、文科省は依然として現場を縛る。2単位でやれ、教科書を使え、世界史探求(従来の世界史Bに相当)や日本史探求と同じ学年では履修してはいけない、評価方法は3観点でやれ、といった具合に。学校教育には自由は与えない、「倭寇」的自由は許さないこうした姿勢を考えると日本はやはり固い社会だと感じ、これに対抗する気持ちが湧いて来る。
1 小川は「現地で史料にあたり実証的に歴史像を描こうとする歴史学が一般的になるにつれて、大塚の著作は・・急速に参照されなくなります。」(p.6)としているが、最近、代表的著作は次々と文庫等で出版されている。『近代欧州経済史入門』(講談社学術文庫、1996年)、『欧州経済史』(岩波現代文庫、2001年)『資本主義と市民社会』『共同体の基礎理論』(岩波文庫、2021年)。各文庫には適切な紹介と研究史上の位置づけがわかる解説がついている。東大経済学部で経済史を担当している小野塚智二は、かなり売れた概説書『経済史』(有斐閣、2018年)の中で、大塚の共同体論を取り上げ、検討している。
[2] ② イギリスの歴史と日本や中国の歴史を比較するとき、イギリスを基準にして日本や中国の発展の度合いを考察するという方法以外に、どのような比較のあり方が考えられるだろうか。③「近代」のヨーロッパが生み出した「自由」と「豊かさ」にはどのような限界があっただろうか。④「近代」の世界の構造が浮かび上がるような世界商品には、砂糖の他にどのようなものがあるだろうか。また、日本や中国と「近代」の世界との関係を見るためには、どのような「世界商品」に着目すればよいだろうか。⑤資本主義の興隆において、イギリスが「植民地帝国」であったことが大きな意味をもっていたのに対し、日本の資本主義の興隆において植民地はどのような役割を担ったのだろうか。⑥18世紀までに世界各地に形成された伝統社会の特徴は、その後の産業革命や国民国家形成の新しい動きに、どのような影響を与えたのだろうか。⑦「近代」の時代は、「近世」の時代から、どのような制度・規範・社会の特徴を受け継いだのだろうか。また、どのような点で「近代」は「近世」と断絶したのだろうか。以上引用pp.71-72