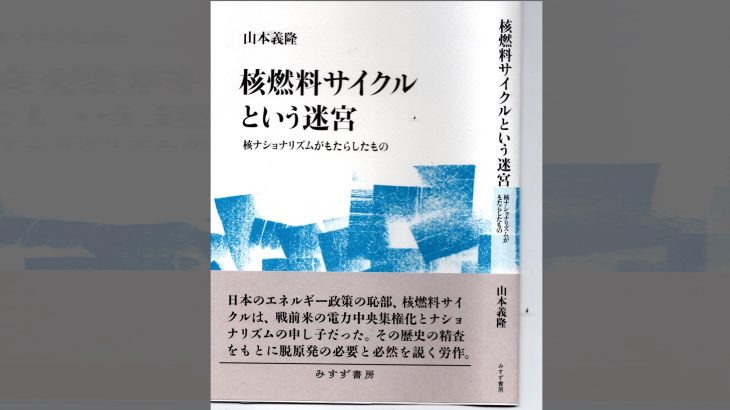――『東京裁判』(赤沢史郎)・『考証東京裁判』・『東京裁判研究』・『私たちと戦後責任』(3冊とも宇田川幸大著)を読む。
天野恵一
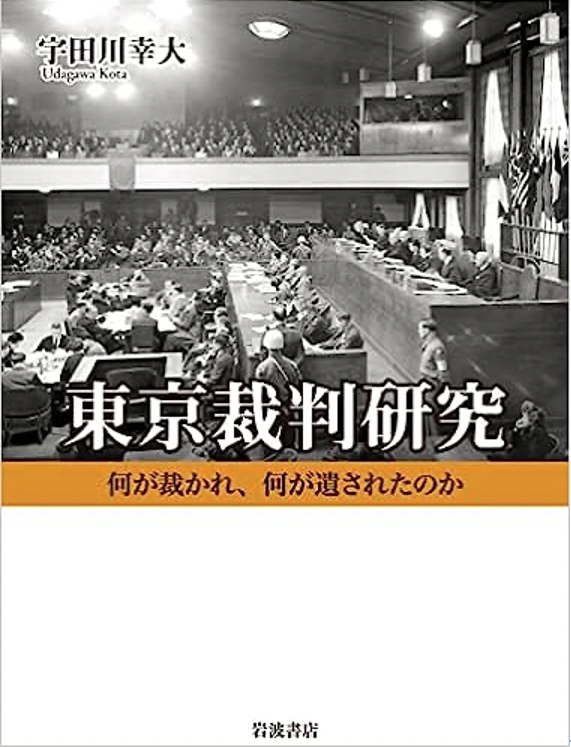
敗戦の翌年(1946年)5月3日にスタートした極東国際軍事裁判。この「東京裁判」の判決公判は1948年11月4日。判決文は1週間かけて朗読され、戦犯25被告に有罪判決(11月12日)。絞首刑は東条英機、板垣征四郎、木村兵太郎、土肥原賢二、広田弘毅、松井石根、武藤章の7人(11月13日執行)。
赤澤史郎はその判決の性格を、こう語っている。
「絞首刑の判決を受けた被告はその全員が、訴因第五四<通例の戦争犯罪を命令、授権もしくは許可した罪>か、訴因第五五<故意または不注意によって戦争法規違反の防止義務を怠った罪>のいずれかで有罪を認定された被告であった。つまり絞首刑の宣言の決め手となったのは、侵略戦争の共同謀議に参画した事ではなく、日本軍の犯した残虐行為に対し責任を負うべき地位にあったかどうかという点に置かれていたといえよう」(『東京裁判』岩波書店)。
この「東京裁判」をめぐる広い問題を、すこぶる簡潔にまとめたブックレットの刊行は1990年である。それは以下のような主張で結ばれている。1985年8月15日の中曽根康弘首相の靖国神社公式参拝という事態がつくりだし続けている状況を踏まえての言葉である。
「しかし、この中曽根前首相をはじめとして、こんにちの支配層の人びとがしばしば口にするのは、今こそ『東京裁判史観』を克服しなければならない、という題目である。『東京裁判史観』とは、第二次世界大戦の立場に立つ不当な歴史解釈のことをさしており、戦争中の日本国家の行動を全面的に誤ったものと断定し、日本人の誇りを失わせるような歴史観であるという。ではその人たちがいう正しい歴史観とはなにか。それは東京裁判の弁護側主張と基本的に同じもので、日本の戦争が侵略戦争であったことを否定し、日本軍が残虐行為をはたらいた事実を否定する歴史観である。/ だが、日本人の誇りとはなんであろうか。自国の行動のすべてを、事実を偽ってまで無理やりに弁護することが、ほんとうに日本人の誇りを保つゆえんなのだろうか。たとえわたしたちにとって、過去の醜行を認めることが苦痛であっとしても、自国の誤りを誤りとして正視することこそ、必要なことではないだろうか。/ もし過去の誤りを正視するなら、かつて国家が誤って戦争の道へ進もうとしたとき、それを批判し、国家の進路を正そうとした人びとの姿も、わたしたちにはっきりと見えてくるであろう。そうした人びとがわずかでも存在したことは、一筋の希望を与えるものだ。またそこに、日本人としての誇りを見出せるのではないか。/ 東京裁判には幾多の矛盾がはらまれていた。しかし東京裁判の問題は、日本の戦争責任の問題をいっそう深める方向で考えられねばならないのではないか。そうしてこそはじめて、アジア諸国など世界の諸国民との真の友好関係も、築きあげられていくにちがいない」(傍線引用者)。
いま、こうした思想視座を共有しながら、細かい審議過程の分析を豊富に織り込んだ、より若い世代の「東京裁判」研究が、この間、浮上してきている。そのテキストの紹介が、今回の課題である。
宇田川幸大の『考証東京裁判~戦争と戦後を読み解く』(吉川弘文館)が刊行されたのは2018年である。
宇田川は、まず『東京裁判を読み解く視点」について、こう語っている。
「膨大な被害を生んだ日本の戦争を、東京裁判はどのように裁いたのか。戦後の世界や日本で、戦争に被害のうち、何が看過され不可視化されてしまったのか。その一端を、東京裁判をめぐる一連のプロセスから具体的に描き出す。これが本書の目的である。/ だが、膨大な関係資料を読み解くには、確固たる視座が求められる。数ある現代史の研究テーマのなかでも、東京裁判ほど検討材料が豊富なテーマは珍しい。日本の国立公文書館で数千冊の戦犯裁判に関する記録が公開されるなど、現在、閲覧できる資料は際限なく拡大している」(傍線引用者)。
「第一に、日本軍の残虐行為、戦争犯罪を生んだ根本原因について、どこまで追求のメスが入れられたのか、という問題がある。なかでも、他のアジアの人びとに対する差別の問題は重要である。日中戦争に従軍し中国人の刺殺訓練(初年兵など、戦場経験の浅い者に、中国人の住民や捕虜を小銃につけた銃剣で突き殺させる訓練のこと)に参加した経験を持つ、近藤一はこう回想する。『二名の無抵抗の中国人を刺し殺しても、「たかがチャンコロを殺したに過ぎない」という意識しかないわけです』」(傍線引用者)。
「東京裁判を検討するには、こうした差別意識の問題、さらには、暴力の行使を容認・当然視する、帝国主義・植民地主義、レイシズムといった考え方、発想そのものを議論の俎上に載せる必要がある」(傍線引用者)。
「第二は、日本の行った戦争をどのように位置づけ、認識するのかという戦争観の問題がある。東京裁判では、日本と連合国、そして時には被告人の間で様々な戦争観が衝突している。日中戦争やアジア太平洋戦争は自衛なのか侵略なのか、戦争の責任は陸軍と海軍のどちらにあるのかなど、東京裁判の一連のプロセスでは、日本の戦争責任やいわば『歴史認識』をめぐる深刻な対立が生じている。当時の被告人や法廷全体が、日本の戦争をどのように捉え、評価したかを検討することは、現在の歴史認識問題や、先に触れた不可視化された戦争被害の問題を考える上で、不可欠の材料を提供することにもつながる。/ 以上、二つの視点を重視しつつ、『東京裁判の前史→検察側・弁護側の裁判準備→審理の過程→判決→サンフランシスコ平和条約の調印』という、これまであまり体系的に論じられたことのない一連のプロセスを、諸資料を読み解きながら再検討していきたい」(傍線引用者)。
膨大な資料を読み抜き、こうした課題が、本書では着実に果たされている。
宇田川は、2022年には、より大作である『東京裁判研究~何が裁かれ、何が遺されたのか』(岩波書店)を刊行している。
著者の東京裁判研究の基本モチーフは前著から一貫している。「序章」で著者は、これまでの東京裁判研究の4つの重要問題があると語り、以下のように論じている。
「第一は、東京裁判の審理に関する分析が充分に行なわれてこなかったことである。これまでの裁判研究は、事実上、天皇・天皇制研究、もしくは『十五年戦争』研究の延長として行われてきた側面があり、裁判の法廷外(特に、水面下での日米側のやりとり)で、天皇や重大な戦争犯罪がいかに免責されたのか、及び、関係者が戦前・戦中の重要事件に関し、検察に何を語ったかについては、早くから注目が集まっていたのに対し、法廷内で、被告人や関係事件がいかに裁かれたのかについては、必ずしも関心が高まらず、研究が遅れる傾向にあった。裁判に提出された証拠・証言は、裁判そのものの検討のためでなく、日独伊三国軍事同盟など、戦前・戦中の政治外交史を検討するための『材料』として用いられることが多かった。審理を扱った研究も、ある特定の事件の実体解明や戦後における『不処罰』を解明しようとするものが多く、裁判研究の枠組から審理検討されることは少なかった」。
第二の問題点は「弁護側の分析が充分に行われてこなかったことである」。
第三は、「裁判の関係者(特に有期刑となった被告人やA級戦犯容疑者など)が裁判をどのように認識していたのか、あるいは戦後日本政治・社会が、裁判をどのように認識してきたのか、という問題が充分に検討されていない。もちろん、裁判の民衆史・社会的検討が全く行われてこなかったわけではない」。「しかしながら、サンフランシスコ平和条約発効以降、すなわち占領期以降から現在にかけての東京裁判に対する世論や、戦後政治における東京判認識は、いまだ総合的検討が行われておらず、裁判後の日本政治・社会における裁判理解にいかなる欠落や問題点があるのか、といった問題は体系的に論じられてこなかった」。
「第四は、先行研究において、課題設定と結論とが充分にかみ合っていないケースがみられる、ということである」。
「これまでの裁判研究が多くの史実を解明し、貴重な視角を提供してきたことは間違いない。だが、検察側・弁護側双方の方針を丁寧に把握しつつ、裁判審理の抱える特徴・問題点を明らかにするという基本的な作業がなされぬまま、裁判論が展開されてきたことも事実である。さらに、東京裁判が戦後の日本政治・社会の中でどのように受容、あるいは忘却されてきたのかについても、戦後史全体における見取り図が描かれていない状況にある。こうした諸状況を踏まえるならば、東京裁判は、未だに歴史事件として充分に『歴史化』されていない、といってもよいであろう。裁判研究の水準を向上させるためには、これまで解明されてきた『開廷史』・『終結史』・『裏面史』だけでなく、審理自体、そして『裁判後』を見据えつつ、歴史の見地から実証的かつ多面的に裁判を分析することが不可欠である」。
こうした問題視角から、宇田川は、すこぶる膨大な審理自体を丁寧に、立体的に読み抜き、平明に分析し、本書をまとめている。目次を示そう。第一章は、『東京裁判と軍部~陸海軍の比較から』、第二章『東京裁判と外務省』、第三章『東京裁判と大蔵省」、第四章「東京裁判における天皇・天皇制論議」、第五章「序列化された戦争被害~東京裁判の審理と『アジア』」、第六章「裁きと戦犯の『戦後』~戦犯の戦争責任観・戦争観・戦後社会観」、第七章「戦後史と東京裁判認識~1945年~2020」、ラストが、分析提示した課題の論点をさらに深化させるための「新しい課題」を設定してみせる作業を示している「終章」である。
この、たいへんな力作を、私たちが長く続けている、共通テキストに感想をぶつけ合う読書会「<戦後>研究会」のテキストとして読んだ時、当然にも教えられることが多いと共感の声が多かった中で、私より年配(60年「安保世代」)の参加者から、第七章「戦後史と東京裁判認識」への疑問(自分の時代体験との違和感)と批判が提示された。私もこの章の「新聞」や「国会」(論議)に登場した「東京裁判」という言葉の分量の多少と認識のベースに置いた、課題の整理・検証については、他の章の緻密な検証作業と比較して、えらく粗削りという印象を持った。
著者は、その後、『私たちと戦後責任~日本の歴史認識を問う』という岩波ブックレットを書いている(2023年2月7日)。これを読んで(テーマは戦争責任・戦後責任の戦後史である)、私自身の違和感の意味がよくわかった。戦後の時代(非転向で出獄したリーダーを中心にした日本共産党ブームで、革命幻想に振り回されたあの時代)の「革命運動」の中心テーマは「戦争責任」の告発であった事実、その共産党になだれ込んだ人びと(転向し、翼賛運動に走った自分の過去を不問のまま、他者断罪をくりかえすのみ)の政治主義への幻滅が、すぐ大量に拡大した時代(これへの倫理的かつ論理的断罪が、多様な「新しい左翼」運動のバネをつくりだしていった時代)、この民衆運動自体の力強く、しかし残念ながらすぐ内部崩壊してしまった動向が、歴史的視座からほぼ排除されてしまっている、「東京裁判」批評中心の一章「占領政策と日本~何が問われ、何が問われなかったのか」。
大激動の、敗戦・占領期から60年安保闘争へ、そしてベトナム反戦・沖縄闘争・大学反乱の60年代末へ、さらに…。こうした歴史の政治的社会運動の多様な動きのプロセスで<戦争責任・戦後責任>がどう問われてきたのか(「東京裁判」とその判決後の歴史も、このベースの上で検証され続けなければならないのでは)。
宇田川の力作を読み続けることで、自分たちの運動史のテーマがよりクリアになった。その意味でも、貴重な読書体験であった。