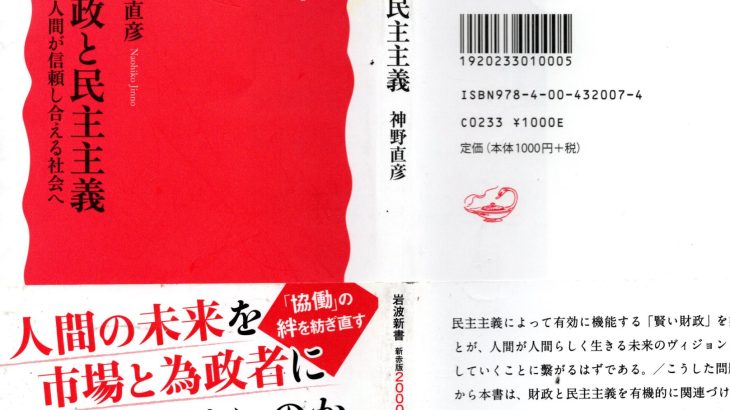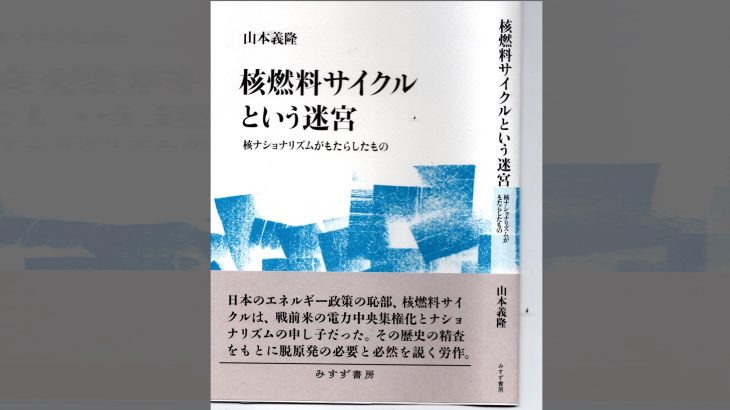白川真澄
てんこ盛りのメニューを並べ立てた「異次元の少子化対策」。これによって政権支持率の浮上を狙った岸田首相だが、その目論見はみごとに外れつつある。
内閣支持率が急落しているが※、その最大の理由は、相次ぐトラブル発覚でマイナンバーカードの利用拡大への不信が一気に高まったことにある。これに加えて、目玉政策の少子化対策への幻想が破れたことも理由として大きい。少子化対策に「期待できない」が73%と、「期待できる」の26%を大きく上回っている(1)。
これほど多くの人びとが「期待できない」とするのは、なぜか。3.5兆円にも上る肝心の財源の確保を先送りする政権の姿勢から、一連の政策が空約束に終わることを感じ取っているからだろう。さらに、財源について「実質的に(国民に)追加負担を生じさせない」という岸田の発言の欺瞞性を見破り、不信を募らせている。この発言を「信頼できる」という人は26%にすぎず、「信頼できない」人は72%に上っている(2)。さらに、子育てへの経済的支援の強化ばかりを打ち出した「少子化対策」そのものに重大な欠落があると見抜いている人も少なくないはずだ。
本稿では、大きな政策的争点になっている「異次元の少子化対策」を批判的に検討し、防衛費倍増と併せて巨額の財政支出を賄う財源をめぐる論争に切り込みたい。
※内閣支持率
NHK(6月9~11日)/支持43%(前月より-3ポイント)、不支持37%(+6ポイント)
朝日新聞(6月17~18日)/支持42%(-4ポイント)、不支持46%(+4ポイント)
読売新聞(6月23~25日)/支持41%(-15ポイント)、不支持44%(+11ポイント)、)
※注1:朝日新聞の世論調査23年6月17~18日
注2:同上
なぜ、少子化が急激に進んでいるのか
昨年(22年)生まれた子供の数は77万人と、初めて80万人を割った。ここ10年近く毎年5%のペースで出生数が減っている。その結果、昨年の合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの数)は1.26と、2005年と並んで過去最低にまで落ち込んだ。2005年をボトムにして2015年には1.45に回復したが、その後はコロナ禍の影響もあって低下の一途を辿ってきた。人口置き換え水準(人口維持に必要な出生率)2.06~2.07には到底及ばず、人びとの「希望出生率」1.8との間にも大きな開きがある。少子化の進行は日本だけの現象ではないが、日本のそれはいちじるしく急激である。
急激な少子化が深刻な問題なのは、国力の衰退や経済成長のダウンを招くからではない。小学校の統廃合や鉄道・バスの廃止など地域社会の崩壊が進むからである。また、社会保障の世代間助け合いの仕組みが機能不全に陥るからである。
日本で少子化が急激に進んでいる理由の1つは、子育てや教育にかかる費用が増大しているにもかかわらず、その多くが家族の自己責任にされていることにある。いいかえると、子育てに対する公的な経済的支援がいちじるしく弱いことにある。
子どもを持たない理由は、「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」がトップ(56・3%)になっている(1)。例えば、生まれてから大学卒業まですべて公立を利用しても、教育費が子ども1人当たり約1000万円かかる。中学から大学まで私立にすると、自宅通学でも約1800万円が必要になる。ところが、最もお金がかかる大学教育の費用は、5割が家計負担になっている。給付型奨学金や授業料減免の措置もやっと導入されたが、所得制限があって利用は1割ぐらいに限られている。
児童手当は所得制限があり、中学生(15歳)までの支給である。保育サービスでは、保育士の数が慢性的に不足している。そのため、1人の保育士が世話する子どもの数は、3歳児で20人、4歳児で30人にもなり、目が行き届かない。イギリスやドイツでは、保育士1人で15人を世話する。あるいは、子どもを保育所に預ける優先順位で、パート就労や求職活動中の人は、正規の共稼ぎ夫婦よりも不利な状態に置かれている。
育児休業給付金は、休業前の賃金の67%しか支給されない。したがって、賃金の低い人が休業した方が損失も少なくなるから、妻が休業することになる。また、子どもを持てば、住宅も広いものにする必要が出てくる。しかし、持ち家政策をとってきた日本では、ほとんどのOECD諸国にある公的な住宅手当がないのである。
こうして、子育て支援に対する日本の公的支出は、対GDP比で1.79%と、OECD諸国平均の2.34%を大きく下回っている。子育てへの公的な経済的支援の大きさは、出生率の高さを規定する要因の1つになっている。

少子化の急激な進行の第2の理由は、育児の負担が女性に過重にかかっていることである。すなわち、性別役割分担が根深く存続しているジェンダー不平等の構造の存在である。そのため、女性には‟就労を選ぶか、出産・子育てを選ぶか”という不条理な二者択一が強いられている。その結果、出産、とくに第2子の出産を諦める女性が少なくない。第1子の出産後に仕事をやめる女性は、かなり減ってきたとはいえ、それでも半数近く(47.0%、2010~14年)いる。
育児に費やす時間は、日本では女性の方が圧倒的に多い。6歳未満の子どものいる夫婦の育児時間は、妻の3時間45分に対して夫は49分と、5分の1にすぎない。米国では、妻2時間18分に対して夫1時間20分、ドイツでは妻2時間18分に対して夫59分となっている(2)。これは、男性の正規労働者がいまなお長時間労働に縛られているという働き方から来ている。週の労働時間が60時間を超える労働者は、30歳代男性では14.7%(2017年)にも上る。
第3の理由は、若い世代が置かれている低所得で不安定な労働・生活環境である。非正規雇用で働く人が全体の4割近くにまで急増し、結婚や子育てといった将来像を描くことさえできない若者が増えている。若い世代の所得分布は、1990年代後半から低所得層にシフトしてきた。配偶者のいる男性(30~34歳)は、所得の高い層(年収500~699万円)では72.1%であるのに対して、低所得層(年収200~249万円)では36.9%にとどまる。また、正規雇用では57.8%だが、非正規雇用では23.3%にすぎない(3)。
雇用の格差にもとづく所得格差の拡大が、結婚や子育てへの意欲や実現に関する格差を広げ、最初から諦める人を増大させている。
※注1:『少子化対策白書』2019年版
注2:『男女共同参画白書』2018年版
注3:『少子化対策白書』2016年版
岸田政権の「少子化対策」とは
岸田政権は、6月13日にその少子化対策を「こども未来戦略方針」として公表した。「経済的支援強化・若い世代の所得向上」、「子育てサービス拡充」、「共働き推進」を3つの柱にし、「加速化プラン」として緊急に取り組むべき施策を列挙している。

その中心は、経済的支援の強化の柱となる児童手当の拡充(24年度中~)である。すなわち、所得制限を撤廃し、支給期間を高校生まで延長する。高校生にも毎月1万円を支給、第3子以降は0歳~高校生で月3万円(現在は0~2歳に月1万5000円、3歳~中学生に月1万円、第3子以降は小学生まで1万5000円)。
それ以外に、次のようなメニューが並べられている。
*働いていなくても子どもを預けられる「こども誰でも通園制度」を創設する(24年度~)。
*育児休業給付金を賃金の80%に引き上げる。育休中は税・社会保険料が免除されるので実質100%の手取りとなる。
*出産費用に保険を適用する(26年度をメドに検討)。
*大学院修士課程に授業料後払い制度を導入する(24年度~)。
*「年収の壁」(106万円、130万円)を越えても手取り収入が逆転しないように、労働時間延長や賃上げに取り組む企業への補助金を出す。
*子育て世帯が公営住宅に優先的に入居できる仕組みを導入する。
これらは、これまで野党や市民が主張してきた政策を丸ごと取り入れたものになっている(ただし、給付型奨学金の全面的な導入や公的な住宅手当の創設などは見送られている)。なかでも児童手当の所得制限は、政府・自民党が選別主義の立場から拘泥してきた争点であった。これを何の説明もなく覆して、普遍主義を採り入れたのである。
これらの対策に必要な財源は、年約3.5兆円とされている。そして、2030年代初頭までに、子ども家庭庁の予算(今年度は4.8兆円)を基準にして、国の予算を倍増するとしている。しかし、安定した財源をどのように確保するかは何も決めず、「28年度までに安定財源を確保する」と先送りしている。
たしかに、経済的支援という点では、これまでよりもずっと内容が拡充されている。政府の経済財政諮問会議は4月26日、経済的支援(児童手当や住宅支援など)を対GDP比で1%、約5兆円増やすと、出生率が0.05~0.1上がると試算している。
何が欠落しているか
しかし、この少子化対策には、重大な欠落がある。経済的支援の拡充だけでは少子化に歯止めがかからないからである。世界各国の経済的支援策の効果を検討した山口慎太郎は、児童手当や育休給付金や税額控除といった「充実した現金給付は必ずしも出生率の引き上げにはつながらない」(1)と指摘している。そして、保育サービスの拡充は、母親の就労を促進する効果をもつが、出生率の向上という面では児童手当の増額よりは一定程度効果がある、と述べている。
子どもを安心して産み育てるためには、何よりも育児の負担がもっぱら女性に負わされている構造、つまりジェンダー不平等を抜本的に改革する必要がある。山口も、「妻の負担軽減に焦点を当てた政策が、出生率の向上につながる」と結論している。
この点で、示唆的なのは、ドイツの「時間政策」である。出生率の低下に悩まされていたドイツは、児童手当など経済的支援を中心にした政策を転換し、家族で過ごす時間を確保できる政策を推進してきた。労働時間の短縮、父親による育休取得の促進、地域での余暇活動である。その結果、子どもと過ごす父親の時間は、平日の1.9時間(1993年)から3時間(2019年)にまで増えた。その分、妻の育児負担が軽減されたことになる。その結果、2005年には1.4を切っていた出生率は、2021年には1.58に持ち直した(2)。
しかし、岸田政権の「こども未来戦略」は、ジェンダー不平等の問題に真正面から切り込まず、この不平等を固定化している男性の長時間労働が温存されている構造を大胆に変革する課題を棚上げしている。労働時間の大幅な短縮のための強力な規制、パートとフルタイムの労働者の賃金格差の解消といった課題は、少子化対策と切り離され放置されている。
さらに、若い世代のなかで「自分たちは結婚や子育てには無縁だ」と考えている人びとの労働・生活環境をがらっと変えることが問われている。そのためには、使い捨ての非正規雇用を増やしたり正規労働者との格差を是正しない雇用構造を抜本的に変革しなければならない。だが、岸田政権は、経済成長のための賃上げは呼号しても、雇用構造を変革する課題には向き合おうとしない。
これでは、急激な少子化の進行に歯止めをかけることはできない。
※注1:山口慎太郎『子育て支援の経済学』(2021年、日本評論社)
2:日経新聞2023年6月18日
どうする少子化対策の財源
経済的支援の大幅な拡充を盛り込んだ少子化対策は、毎年3.5兆円もの新たな追加財源が必要とされる。これについては、次のように想定されている。
まず、「実質的な国民の追加負担を生じさせず、増税を行なわない」ことが前提にされる。その上で、(1)医療・介護など社会保障の徹底した歳出改革を行なう(1.1兆円)。(2)社会保険料(健康保険料)に上乗せする「支援金制度」を創設する(0.9~1.0兆円)。(3)すでに確保した予算を最大限に活用する(0.9兆円)。(4)足りない分はつなぎ国債として「こども特例国債」を発行する。なお、(2)の支援金は、国民1人当たり数百円(500円)を健康保険料に上乗せして徴収するが、保険料の伸びを抑えることで実質的な負担が増えないようにする、と説明されている。
ここで見すごせないのは、少子化対策の財源は、防衛費の倍増とそのための財源確保を最優先するという方針によって大きく制約されている、ということである(1)。いいかえれば、防衛費倍増の財源調達に従属するという縛りがかかっているのだ。
防衛費は、「台湾有事」を煽り立てて「反撃能力」(中国本土を先制攻撃できる長射程ミサイル)を保有するために、23~27年度で43兆円に大増額する。そのため、新たに14.6兆円の追加財源の確保が必要とされる。そこで、(1)4.6~5兆円を「防衛力強化資金」として賄う。外国為替特別会計などの剰余金、国有財産(大手町プレイス)の売却、コロナ対策のための医療関係の独立行政法人の積立金の返納など。(2)3.5兆円を決算剰余金の活用で調達する。(3)3兆円強を社会保障以外の歳出改革で捻出する。(4)それでも3兆円(27年度では1兆円)が不足するので、増税(法人税、所得税、たばこ税の増税)で賄う。
防衛費の財源調達で特徴的なことは、増税を明確に打ち出したことである。ただし、増税の開始時期は、25年度以降にずらされる見通しである。これは、アベノミクスを信奉する自民党内安倍派が増税に反対し、国債発行に頼ることを強く主張しているからである。萩生田政調会長は、「2年は国債で」と主張したり、一般会計のなかの国債償還費を防衛費に流用することを提案している。
とはいえ、増税を防衛費の財源の1つにすると決めたことは、子育て支援など社会保障の拡充のために増税する道をあらかじめ封じてしまったことを意味する。事実、岸田は、少子化対策の財源として「消費税など増税を行なわない」と繰り返し断言している。
巨額の財政支出を賄う財源としては、(1)増税、(2)社会保険料の引き上げ、(3)歳出改革、(4)国債増発という4つの方策がありうる。もちろん、負担を公正なものにする工夫をしながら最も安定した財源確保を可能にするのは、増税である。しかし、防衛費の財源確保を最優先したために、少子化対策のために増税という方策をとることができなくなったのだ。ここから、最悪の財源構想が出されてくることになる。
※注1:防衛費の倍増については、拙稿「大転換する日本の政治と財政」(「テオリア」23年6月10日号、7月10日号、8月10日号)を参照されたい。
歳出改革/医療・介護のサービス削減と自己負担増
少子化対策のために必要な3.5兆円の追加財源の第1の柱は、社会保障の徹底した歳出改革である。すなわち、医療や介護のサービスを削減すると同時に、利用者の自己負担を引き上げる、ということである。
歳出改革の内容には、DX(デジタル化)による薬や検査の重複回避も含まれているが、次のようなことが想定されている。後期高齢者の医療費の2割負担および介護サービス利用の2割負担の対象を拡大する。診療報酬・介護報酬を見直す。病院・病床の集約による効率化を図る。
後期高齢者の医療費の2割負担は昨22年10月から導入されたが、その対象になったのは約20%、370万人である。政府はもともと、2割負担をすべての後期高齢者に適用することをめざしていて、さらに所得の低い人にまで拡大しようとしている。医療や介護の自己負担が2割になる人が増えれば、利用を控える人が続出する。つまり、サービスから排除される人が増えることになる。子育て世代への給付を増やすためにその負担を高齢者に負わせるのは、世代間の対立・分断を強める悪質な政治であり、許されない。
さらに、24年度には診療報酬と介護報酬が同時に改定される。私たちは、コロナ・パンデミック時に生じた医療のひっ迫を痛いほど経験した。また、介護人材の不足は深刻で、2025年度に約32万人、40年度には約69万人が不足すると予測されている。したがって、診療報酬における薬価部分を引き下げるとしても、本体部分や介護報酬の引き上げが必要とされている。その抑制や引き下げは、あってはならない。
医療や介護の歳出改革は、高齢化の急速な進行やコロナのような感染症流行に対応するケアの拡充が求められている時代の流れに逆行する。
社会保険料の引き上げは許されない
第2の柱は、社会保険料の引き上げである。具体的には、500円程度の「支援金」を健康保険料に上乗せして徴収する。
岸田首相は、社会保障の歳出改革によって保険料の上昇を抑えられるから「実質的な追加負担が生じない」と弁明したが、保険料を引き下げるとは言っていない。支援金分が保険料の引き上げになることは、誰が見ても明らかだ。7割を超える人が、岸田の発言を信頼できないと思ったのは、当然である。
社会保険料(医療・年金・介護)の負担は、ここ10数年間、所得税の負担が増えていないのとは対照的に増え続けてきた。その結果、日本は、国民負担率(46.8%、23年度)のうち社会保険料の負担が18・7%と、ひじょうに高い割合を占める国になっている。
社会保険料の負担は家計を圧迫し、これ以上負担できないような高い水準に達している。その平均料率は、勤労者世帯では所得の約30%にまでなっていて(1)、健康保険料負担の平均は月2万2058円である(2)。
社会保険料のさらなる引き上げは、もはや限界に来ている。国民健康保険料を一部でも滞納している世帯は245万世帯、全体の13・7%にもなる(2019年)。さらに保険料を引き上げれば、支払えない人びとが増えることは明らかだ。また、社会保険料を引き上げれば、企業負担が増えるため、それを逃れようと非正規雇用を増やすことに拍車をかける。
そもそも、社会保険料は、定額=均等割の要素があるため、低所得層の負担が相対的に重くなる逆進性がある。また、保険料を賦課する報酬額に上限を設けているため、富裕層に有利になっている。国民健康保険料の負担率が低所得層ほど重いことは、次の表を見れば分かる。したがって、社会保険料を思い切って引き下げ、累進性のある税に置き換えることが求められている。
表1 国民健康保険料の所得階層別の負担率
所得 負担率
100~150万円 12・5%
300~400万円 10・2%
700~1000万円 7・5%
(厚労省「国保実態調査報告」2011年)
にもかかわらず、岸田政権が社会保険料の引き上げに走ろうとしているのは、増税よりもずっと抵抗が小さいからである。増税、とくに消費税率の引き上げに対する抵抗感は、日本では際立って大きい。
東京財団によるアンケート調査(22年10月)によれば、消費税率の引き上げに関して「経済学者」の56.7%が賛成した(「現状維持」が30.9%)のに対して、「国民」の賛成は7.9%にとどまり42.35%が税率引き下げ・廃止に賛成している(「現状維持」が40.9%)。この強い租税抵抗感は、何よりも政府や政治に対する信頼の低さから来ている。
※注1:日経新聞23年4月21日
注2:同23年5月19日
国債依存への安易な発想の横行
強い抵抗を呼ぶ増税の必要性を真正面から打ち出すことを回避する姿勢は、与野党を問わず日本の全政党に共通している。なかでも減税ポピュリズムが際立つのは、ネオリベ改革派の維新の会とMMT(1)に依拠するれいわである。増税に代わる財源案として主張されるのが歳出改革、あるいは国債増発である。
政府・自民党も同じで、国債発行への安易な依存がたえず顔を出す。防衛費倍増の財源についても国債依存がむし返される余地があるが、少子化対策の財源としてはつなぎ国債として「こども特例国債」の発行が予定されている。つなぎ国債は、返済のための償還財源(税項目)を法律に明記して発行するものである。ところが、岸田政権は、償還のための税項目をいっさい明らかにしていない。明らかにすれば、将来の増税を明言することになるからだ。つまり、「つなぎ国債」と称していても「赤字国債」発行の隠れ蓑にすぎない。ごまかすことしか特技のない岸田らしいやり口である。
いうまでもなく、日本の財政は、すでに国債頼みの運営にどっぷり浸ってきた。23年度の政府予算では、税収が過去最大の69兆4400億円と見込まれている。前年度予算より4兆円以上増えるのだから、国債の新規発行を4兆円減らしてよいはずである。だが、国債発行は32兆6230億円と、1.3兆円しか減らしていない。まして、22年度の税収実績は71兆1373億円と過去最高になり、見込み額を6兆円近く上回った。企業の利益急増による法人税収の伸び、3%のインフレ=物価上昇による消費税収の増大などが税収を大きく押し上げたのである。今年度も同じ高水準の税収が確保できるとすれば、新規国債発行額をさらに減らし、国債依存度を下げることが可能である。
このことを妨げるのは、防衛費の倍増による年4.8兆円もの突出した支出増である。しかも、政府は、税収増による決算剰余金の増大分まで防衛費の財源に回そうとしている。予想以上の税収増は、想定された1兆4000億円をはるかに上回る2兆6294億円の決算剰余金を生みだす。当初はその半分7000億円を防衛費の財源の1つに充てることになっていた(残りの半分は国債の償還に充てることが定められている)が、さらに6000億円を上積みする。これによって、増税の時期を先延ばししようとしている。
今年度の国債の新規発行額は35.6兆円だが、これとは別に膨大に累積した既存国債を借り換えるための借換債を157兆5513億円発行する。新規発行債に借換債、財投債、新たなGX債を合わせると、国債発行総額は205兆7803億円にも上る。その結果、国債残高は、今年度末には25兆円増えて1068兆円、対GDP比では187%になる。アベノミクス開始から12年間だけで363兆円、1.5倍も増える。また、国及び地方の長期債務残高は1279兆円、対GDP比224%に膨らむ。先進国では、飛びぬけて巨額の政府債務を抱えることになる。
※注1:MMT(現代貨幣理論)に対する批判については、拙著『脱成長のポスト資本主義』(2023年、社会評論社)第Ⅱ部第5章を参照されたい。
大量の国債発行が可能であった時代的条件の終焉
国債残高が膨大に積みあがった結果、財政運営を脅かす要因が表面化しつつある。国債費(債務償還費プラス利払い費)がじわじわと増えてきているのである。2013~2021年度の国債費は年平均23兆3359億円だったが、22年度は24兆3393億円に、さらに今年度は1兆円近く増えて25兆2503億円になった。国債費は歳出全体の22・1%と、社会保障関係費の32.3%に次ぐ大きな支出項目となっている。その増大は、社会保障関係費など必要不可欠の財政支出を圧迫し、制約する。今後、長期金利が少しずつ上昇することが確実視されるから、利払い費が増えて国債費が増大することは避けられない。国債依存の財政は、こうした形でその限界を現わしつつある。
にもかかわらず、いぜんとして《財源不足は国債発行で補えばよい》とか《財政赤字を恐れず財政支出を拡大すべき》といった主張がまかり通っている。その根拠とされるのが、これだけ巨額の政府債務を抱えていても財政破綻が起こっていない、という現状である。たしかに、(かつてのギリシャのように)高い利子を支払わなくても国債の買い手が容易に見つかり、借金を続けることができている。
なぜなら、新たに発行される大量の国債を日本銀行が(市中銀行経由で)ほとんど買い取っているからだ。日銀が購入して保有する国債は、2012年度の125兆円から22年度には581兆円と4倍以上にも増大し、いまでは国債発行残高の5割を超えるという異様な状態になっている。
国債発行残高が1千兆円を超えるまで赤字国債を発行し続けることができた秘密は、利払い費が低く抑えられてきたことにある。国債残高が急増しているにもかかわらず、利払い費は横ばいで、年8兆円までに収まってきた。そして、このことが可能だったのは、日銀が大規模な金融緩和の継続によって長期金利(10年物国債の利回り)をゼロ近辺に抑えこんできたからである。

政府や日銀は、企業や個人がお金を借りやすくして景気を良くするために金融緩和を続ける必要があると言う。しかし、アベノミクス下の「異次元の金融緩和」は、巨額のマネー(マネタリーベース)を市中銀行に供給したが、肝心の企業自身が積極的な投資や人件費の引き上げを行わなかった。そのため、市中銀行の貸し出しは少ししか増えず、日銀の当座預金として積み上げられた(その額は、2022年3月末で563兆円)。マネーが実体経済を勢いよく動かす経済活性化は、起こらなかった。
そのなかで、政府だけが金融緩和による超低金利政策によって得をしたのである。ゼロ金利の金融緩和策は、政府が利払いを増やすことなく国債を大量に発行できるようにしたからだ。借金財政を続けるために、金融緩和をやめられなくなったのが、真相である。
この間も、他国の中央銀行が急激なインフレ抑制のために金利を引き上げてきたのに対して、日銀は例外的に金融緩和を続けてきた。そのことが日米の金利差の拡大による円安を招き、物価高騰に拍車をかけ、人びとの生活を苦しくした。それでも、長期金利の上限を0.05%に抑え込むために、日銀はいまなお国債を買い続けている。
しかし、世界経済の流れは、《低インフレ・低金利・低成長》から《高インフレ・高金利・しかし低成長》へと転換しつつある。この流れに、日本だけがいつまでも逆らうことはできない。日銀が金融緩和を修正あるいは終了し、政策金利を引き上げる「正常化」に転じることは避けられない。そうなれば、連動して長期金利も上昇する。
金利上昇は、国債の利払いを急増させる。財務省の試算では、10年物国債の想定金利を26年度には0.05%に引き上げただけで、利払いの増大によって国債費は29.8兆円と、今年度よりも4.5兆円増える。金利がさらに1%上昇すれば、8.1兆円増えて33.4兆円に膨らむ。
ゼロ金利の継続で利払い費が増えないおかげで大量の国債発行ができた時代は、終わりつつあるのだ。
日銀による大量の国債保有の大きなリスク
にもかかわらず、国債をどれだけ発行しても《政府の子会社である日銀が買い続ければ、問題はない》と反論する人もいる。金利上昇にともなって政府による日銀への利払いが増大しても、日銀の政府への納付金が増えるから穴埋めされる、というわけである。
しかし、この主張は、金利が上がれば日銀の当座預金の付利の利率(現在は0.1%)もいち早く上昇し、市中銀行への利払いが増えるということを見逃している。それが国債の利子収入を上回って、日銀が債務超過に陥る危険性がある(1)。
さらに、金融機関が大量の債券(国債や証券)を保有している場合、その金利(利回り)が上昇すると債券価格は下落する。買った時の価格(簿価)よりも時価が下がれば、含み損が発生する。この春には、米国のFRBがインフレ対策で行なってきた急激な利上げが、銀行の保有する債券価格を急落させて含み損を増大させ、預金流出によるシリコンバレー銀行などの経営破綻を招いた。これは、581兆円もの国債を保有する日銀が抱えるリスクの大きさを予告している。
日銀は、昨年末に長期金利の変動幅の上限を0.05%に引き上げたが、これによって長期金利がわずかだが上昇し、国債価格が下落した。そのため、日銀保有の国債に8.8兆円の含み損が発生した。さらに、長期金利が1.5%上昇して2%になれば、52.7兆円もの含み損が発生すると試算されている(内田副総裁、3月29日)。
含み損は、金利の上昇幅が大きければ大きいほど、また保有国債額が大きければ大きいほど、大きくなる。たしかに含み損が発生しても、日銀は国債を満期まで保有することができるから、ただちに損失が現実に生じるわけではない。しかし、含み損がどんどん大きくなって財務が悪化すれば、中央銀行としての信認は根本から揺らぐ。また、国債を売却してマネーを吸い上げる買いオペの操作ができなくなるといった制約が課せられる。
これからも国債を大量に発行して日銀に買い取らせればよいという主張は、異常なまでに巨額の国債を保有する日銀が抱える大きなリスクを無視する暴論である。
※注1:河村小百合『日本銀行 我が国に迫る危機』(2023年、講談社現代新書)
財源を何に求めるべきか
それでは、少子化対策をはじめ支出を増やし続けるべき社会保障の財源は、どのように確保されるべきか。
これまで見てきたように、4つの方策のうち社会保障の歳出改革、社会保険料の引き上げ、国債増発の3つは、財源としてまったく不適切である。残された方策は、公正な増税しかない。防衛費を最優先して社会保障のための増税を封じた枠組みを先ず壊し、順序を間違えずに増税を進める必要がある。
第1に、防衛費の増額をやめ、さらに大幅に削減することを最優先する。今年度だけで4.8兆円の増額だから、これをやめれば5兆円近くの財源を確保でき、少子化対策と医療・介護サービスの拡充に充てることができる。さらに、防衛費のなかの装備品購入費や研究開発費約1.6兆円を削る必要がある。「歳出改革」というのであれば、防衛費こそ最大のムダとしてその標的にするべきだ。
第2は、増税は、富裕層と大企業への課税強化から始める。具体的には、金融所得に勤労所得課税なみの累進性を適用する(総合課税にする)。これによって、所得1億円以上の富裕層(約2万7千人)の税負担を重くする(少なくとも3兆円以上の税収増)。また、大企業への法人税率を引き上げる。いま大企業は空前の利益増を享受し、株主への配当や自社株買いを増やしている(10%の税率アップで、約5兆円の増収)。さらに、法人税に累進税率を適用することも有効である(1)。巨大企業の税負担を増やすと同時に、中小企業の負担は軽減される。
第3は、逆進性のある社会保険料を引き下げると同時に医療・介護の自己負担分をなくす。その代わりに、累進性のある所得税の負担を増やす。その上で、低所得層への給付増大を伴う消費税率の引き上げが課題になってくる。ただし、インフレによる物価高が家計を直撃している現在、一時的な消費税減税がありうるとしても、消費税率を引き上げるべき時ではない。
テレビ朝日の世論調査(6月10~11日)によれば、少子化対策の財源として「歳出削減」を選ぶ人が62%と圧倒的多数を占め、「国債の発行」12%、「増税」9%、「社会保険料の増額」7%となっている。
人びとの租税抵抗感がひじょうに強いなかで、社会保障の財源確保には公正な増税が必要だという真っ当な主張は、簡単には受け入れられないだろう。しかし、少子高齢化と低成長・脱成長の時代にふさわしい社会保障と税に関する長期的なビジョンを真正面から対置することが求められている。それは、自民党政権あるいは自民・維新の連合政治と本格的に対抗してリベラル・左派勢力が再生するためには必要不可欠なのだ。
※注1:伊藤周平「大企業・富裕層への課税強化」(日経新聞23年7月3日「あるべき財源論議」㊦)
(2023年7月15日記)