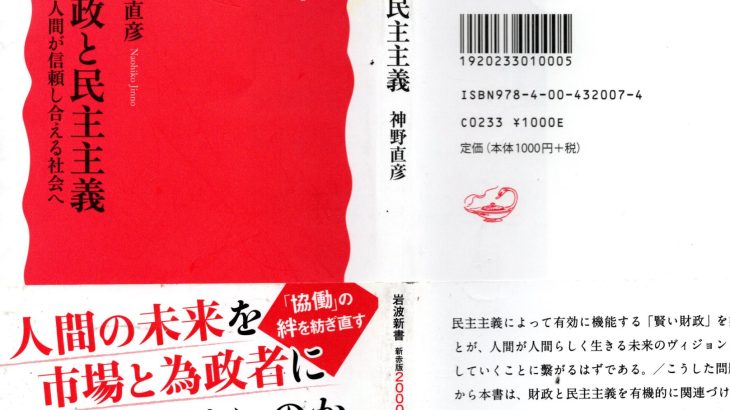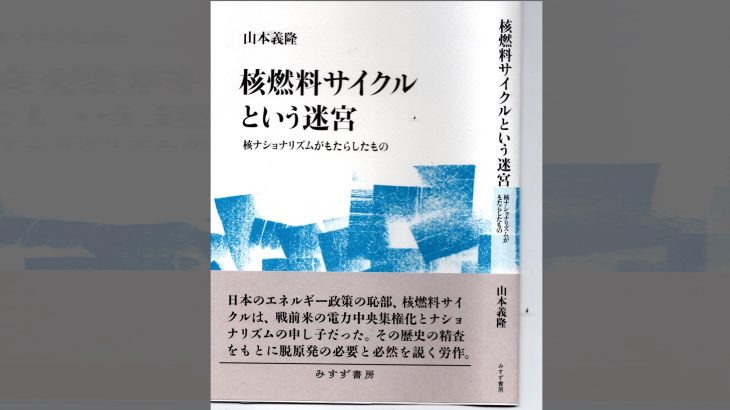大井赤亥(政治学)
PP研では、7月28日の第9回ピープルズ・ムーブメント研究会で「日本維新の会はなぜ躍進したのか」と題して、大井赤亥さんの報告を受けました。当日のパワポによる報告とほぼ内容的に重なる文章が「テオリア」2023年8月10日号に掲載されているので、本人と「テオリア」の了解を得て投稿します。
1993年体制について
私は2022年10月に『中央公論』に「1993年体制と『3・2・1の法則』」という論稿を発表して、現代日本政治の見取り図を提示した。
すなわち、1993年の自民党分裂により、それまでの「保守」と「革新」の対立に加えて、「改革」が新たに政治的選択肢に加わり、「保守・旧革新・改革」の三極構造になったというものである(1993年体制)。
「改革」の顕在化の端緒は、93年に自民党を割って出た保守系三新党、すなわち新生党、さきがけ、日本新党であり、これらは「非自民保守系改革派」と総称できる。それは文字通り、「非自民」でありながら「革新系」ではなく「保守系」で、何をもって自民党に対峙するかといえば「改革」を旗印とする勢力であった。以降、30年間にわたり、この三極が日本政治の政治的選択肢を作ることになった。
行政学者の上山信一が、この三極の政策的理念を簡潔にまとめている。すなわち、「改革」とは「成長、規制緩和、小さな政府」、「保守」とは「公共事業、財政出動、景気対策」、「旧革新」とは「格差是正、大きな政府」だとされる。
「3・2・1の法則」とその変化?
「保守・旧革新・改革」からなる三極構造は、第二次安倍政権が成立した2012年以降、「自公・民主党系野党・維新」によって担われ、その力関係はほぼ固定化されてきた。
すなわち、2022年参院選の全国比例における得票数を見ると、自公は2444万、野党(立国社共れ)は1713万、維新は785万となり、この割合はそのまま「3・2・1」となる。2012年衆院選以降、都合8回の国政選挙の比例得票数を見ても、この三極構造は「3・2・1の法則」とでも呼ぶべき安定的な力関係で推移しているのである。
しかし、このぎこちない三極構造に、変化の兆しも見えている。
与党側でいえば、自民と公明の連立に隙間風が吹くとともに、国民民主は2022年度予算に賛成に転じて与党接近を見せている。野党側では2021年衆院選での野党共闘が挫折し、立憲は中道保守とリベラル左派のあいだで右往左往する積年の宿痾に回帰しつつ、共産党も松竹除名問題などで教条主義的党体質に先祖帰りしている。
野党低迷の間隙を縫うように、維新は次期衆院選での野党第一党を目標に掲げ、自民と維新との保守二大政党による「改革合戦」の構図を描いている。2023年春以降の世論調査では、維新が立憲を支持率で上回る結果が続いており、「自公・民主党系野党・維新」による「3・2・1」の力関係が揺らいでいる。以下、三極それぞれの現状を確認したい。
岸田政権の二年間
岸田政権は、久方ぶりの「宏池会政権」として、自民党にも「聞く耳」が取り戻されるかと思われたが、その性格は、今のところ、明確に定義できない。
経済政策では、コロナ禍で大規模な財政出動が常態化したこと、異次元の金融緩和については政策転換の余地が乏しいことなどから、アベノミクスの大枠を継承する「踊り場の政権」といえる。他方、行財政改革をめぐる「改革」姿勢は鈍化しており、それが「改革」志向の若年有権者のあいだでの支持率低下を招いているとされる。
党内最大派閥の安倍派の意向を受けて防衛費倍増に取り組みながら、その財源として国債を主張するタカ派の声は斥け、増税という「難しい道」を選んだのは宏池会政権としての最低限の矜持なのかもしれない。いずれにせよ、外交や憲法の課題について、岸田政権のこれまでは、「羊の皮をかぶった狼」なのか、「羊の皮をかぶった羊」なのか、判断は難しい。
総じて岸田政権は、既成政党の支持基盤が縮小し、無党派層の政治参加が停滞するなかでの自民党の相対的優位、すなわち「縮小と停滞の一党優位性」にあるといえる。
野党共闘の「複雑骨折」とその後
2021年衆院選での野党共闘は、安倍政権への対抗を最大の結節点として立憲野党が円陣を組んだものであり、反安倍包囲網の意味あいがあった。
しかし、2020年春からのコロナ禍により、政治争点は「安倍一強」への対決争点から、コロナ禍にいかに有効な対策を打てるかという合意争点へと変化した。安倍から岸田にいたる自民党内疑似政権交代によっても、政治の潮目は大きく変化した。
総じて、2021年衆院選における野党の挫折は、コロナを受けて政治の対立軸が「合意争点」に移行した局面変化を前に、安倍政権下の「対立争点」に適応する形で構築された「野党共闘」というフレームで与党に正面対峙した点にあったのではないだろうか。コロナ脱却が有権者の最大の関心事になる中、安倍政権の残存に対する正面攻撃を印象づけては、野党の「ひとり相撲」に映る可能性があったであろう。
これまで民主党系野党は、いわゆる中道改革路線か野党共闘か、対案路線か対決路線かというジレンマを抱えてきたが、立憲は再びそのジレンマに回帰し、右往左往を繰り返している。誰が執行部を担ってもこの状況の打開策はなく、泉執行部に同情もする。
共産党にも課題は多い。立憲との政権協力を掲げるに際して、共産党は自衛隊について「国民的合意をへて廃棄、それまでは活用」と説明するものの、最大の課題は、それが有権者を納得させていないことである。
「共産党が変わろうとしていることは、それなりに評価していますが、他国の例を見る限り、この程度の変わり方では政権を担うのには足りません」(中北浩爾)という指摘はまじめに受け止められるべきだろう。また、松竹伸幸氏の除名問題によって露見された教条主義的な党体質の地金もまた、野党共闘の前途に暗い影を落としている。
連合と国民民主の姿勢
民主党系野党はその支持基盤において連合という応援団を有しており、連合の支援は、民主党系が維新に対して持つアドバンテージ」(中北浩爾)であった。
しかし、連合内でも官公労と民間産別のあいだには今でも越えがたい壁がある。公共セクターと大企業労組では、同じ「労働者」といっても、「民間の仕事は金稼ぐこと、公務員の仕事は金使うこと」といわれるように、その実入りの構造は大きく異なり、それに派生して、政治的要求も異なりがちである。「〔官公労と民間産別は〕政府の個別的な財政的サービスを受ける場合は一致できても、反対に政府のサービスや保護を削減され、自己改革を求められる局面になると内部対立が生じる」(小西秀樹)のである。
しかし、組合員700万という数の力でまとまっていることに連合の影響力があり、その枠を壊すほどのエネルギーは自治労にも民間産別にもない。
この組織力を自民党が脅威と感じるのは当然であり、連合内の不和に乗じて、自民党が民間産別を与党に取り込みたい、少なくとも中立化させたいと思うのは当然である。
連合の側も、「一強多弱」の政党の力関係の下では、個別の政策実現のために政府や与党に直接アクセスすることが必要になる。長らくトヨタ労組は組織内候補として愛知11区に古本伸一郎を擁立してきたが、2021年衆院選では立候補を取りやめさせ、間接的に自民党と歩調をあわせるなど、大企業労組による自民党接近が見られる。そこに、芳野友子連合会長の反共主義や権力志向が重なり、与野党双方に対する連合の距離も流動化している。
22年度予算への国民民主党の賛成も、「政界で埋没したくない」という玉木雄一郎の個人的プレーと、民間産別の与党接近が重なって生じた変化であろう。それを機に国民民主の与党入り、すなわち自公国の連立政権も噂されたが、仮にそうなれば、自民の業界団体に創価学会と民間産別という固い組織票がつくことなり、極めて強固な「2022年体制」が成立されたことであろう(中北浩爾)。
維新による「改革」の独占
これまでも、新自由クラブ、日本新党、みんなの党など、「自民党内の『田中角栄的、竹下登的なるもの』へのアンチテーゼとして」(浅川博忠)生まれてきた保守系改革派の政党は存在した。しかし、その多くが、自民党盤石ゆえにその支持基盤を割れなかったり、創設者の「個人商店」を脱しえなかったり、政界再編につながらない「突発的攪乱要因」に留まってきた。
維新は、自民党を飛び出した「保守系改革派」が作った政党のなかで、これまで最も成功裡に成長しているものである。
維新の特徴は、第一に、2012年以降、「改革」の政策的布置をほぼ独占して担ってきたことにある。
1993年の政界再編以降、規制緩和や民営化など「改革」の政策群を担う政治勢力は、党派横断的に散在しながら変遷してきた。1993年の細川政権やその残党が立ち上げた新進党は「たゆまざる改革」を掲げたが、自民党も橋本行革などで「本当の改革は自民党が行う」と主張し、小泉政権期の民主党も自民党と「改革競争」を唱えた。しかし、2012年に維新の会が国政参入すると、それ以降、「改革」は維新の会がもっぱら独占するようになった。
「わかりやすい争点」となった行財政改革
維新の第二の特徴は、これまで「わかりにくい争点」とされてきた行財政改革を、「わかりやすい争点」へと転化したことであろう。
一般に、政策争点には「やさしい争点(easy issue)」と「難しい争点(hard issue)」とがある。日本政治に即していえば、護憲か改憲か、集団的自衛権に賛成か反対かといった「外交安全保障・憲法」の政策群には分かりやすい争点とされるものが多い。
それに対して、社会保障を賄うのは増税か国債か、年金は賦課方式か積み立て方式かというような「行財政改革・成長」の争点は、有権者にとって、「認知的な負担の大きい難しい判断」であり、また負担やコストの配分を含むので「あまり心地の良くない判断」を強いるものでもある(平野浩)。それゆえ、市民社会の有権者の実質的利害に依拠する争点でありながら、「行財政改革・成長」の争点で政党政治が再編されることは相対的に困難であった。
しかし、2010年代以降、維新はこれをシンプルかつ有権者の肌感覚にそって訴えることで、「わかりやすい争点」としてきた。国会議員や自治体議員の定数削減、公務員の人員削減、自治体の統廃合など「身を切る改革」は、維新によってわかりやすく先鋭的に示された「行財政改革」の争点といえる。
「身を切る改革」を求める素地
私自身、2021年衆院選で候補者として、コロナ禍の飲食店をまわって意見を聞く「どぶ板」活動をしたが、政治に「身を切る改革」を要求する有権者層の分厚さを痛感した。
民間事業者の意識の背景にあるのは痛税感や嫌税感であり、すなわち、自分たちが税金を払っている意識は強いが、自分たちが税金の恩恵を受けているという実感が極めて乏しい。
不況の時に行政が何してくれた? 起業や開店の際には行政指導で様々に細かい注文をつけながら、不景気で苦しい時に行政が何か助けてくれたか? 儲かろうが倒産しようが自己責任。そういう厳しい環境でやってきた。それでいて政治家も官僚も税金で飯食って、国会で居眠りしている。それなら民間と同じように「身を切れ」、というわけだ。
とりわけ、飲食店は基本、日中はテレビをつけっぱなしで、ワイドショーでは橋下徹や吉村洋文府知事が出ずっぱりである。飲食業の経営者は学歴も高くなく、やんちゃなヤンキーあがりの人たちも多く、少々柄の悪い維新の口吻には親近感がある。
このような意識の上に、維新がテレビを通じて喧しく言い立てる「身を切る改革」は、砂漠が水を吸い込むように浸透する。「身を切る改革」は、民間事業者の仕事感覚に即した、「わかりやすい争点」なのである。
維新の全国政党化を阻むもの
しかし、維新が全国政党化するためには、いくつかの死活的な課題もある。第一に、既成政党の多くがナショナルな規模の支持基盤を持っているのに対して、維新にはそのような全国規模の支持基盤がない。
木下ちがやによれば、「政党が全国政党たりうる条件は実は政党そのものにはなく支持基盤がナショナルな規模であるかどうかにおおきくは規定される」。民主党は連合、公明党は創価学会などの中間集団に依拠し、自民党は複数の支持団体に網をかけた多重的な形式であるが、既成政党がナショナルな中間集団とともにあることには変わりない。
維新がそのような支援組織を自力で形成することは困難であり、木下によれば、「当面関西地域以外にも勢力を伸ばして全国化はしていくかもしれないが、全国政党になることはおそらくないだろう」。
第二に、維新が政権与党となるためには、結局、自民党の分裂による何らかの保守政界の再編を待たねばならない。しかし、自民分裂が生じた1993年と違い、現在、自民党に分裂をもたらす要因は乏しく、むしろ、細野豪志や長嶋昭久など、自民党の求心力が他党からの離反者を吸い寄せている。
その意味で、自民党分裂による保守政界の再編という維新のシナリオは、予見可能な未来においては、実現性に乏しいだろう。
政治的選択肢の行方
これからの政党対立の構図について、図式的ながら一つの見取り図を示したい。政治学者のタゲペラとシュガートによれば、二本の対立軸で構成される政治空間においては、必ずしもそれぞれの両極に四つの政党が登場するのではなく、旧来の二極に加えて、新しい対立軸の一方の極端を代表するもう一つの政党が加わり、三極構造になるとされる。
とすれば、1993年の政界再編がもたらした「保守・旧革新・改革」の三極とは、55年体制下の「外交安全保障・憲法」の対立軸に、1980年代以降に顕著になった「行財政改革・成長」という対立軸が重なり、二つの対立軸がもたらした三極構造だといえよう。
そして、「保守・旧革新・改革」の三極構造がどのような力関係で推移するかは、今後、この「外交安全保障・憲法」と「行財政改革・成長」とのどちらの対立軸によって与野党対立が形成されるかに、大きく依存するであろう。
政治学者の平野浩の指摘に基づけば、55年体制を規定した「外交安全保障・憲法」の軸に沿えば、日米安保堅持と憲法改正を共有する点において「保守(自民)」と「改革(維新)」とは同質であり、それらに対して護憲や専守防衛を唱える「旧革新(立憲)」が対峙する。
しかし、「行財政改革・成長」の軸に政党対立を置きかえれば、業界団体に依拠して公共事業や補助金による利益配分を行ってきた「保守(自民)」と労働組合に依拠して格差是正や社会保障を唱えてきた「旧革新(民主党系野党)」とは、「大きな政府」として同質であり、それらに対して双方の「既得権」を否定する「改革(維新)」とが対立する構図が浮かび上がるという。
そして、これからの政党対立は、「外交安全保障・憲法」の軸における「保守+改革vs旧革新」と、「行財政改革・成長」の軸における「保守+旧革新vs改革」との、そのどちらが「自民vs非自民」という対立軸に重なるかによって、その内容が決まるというのである。
「外交安全保障・憲法」をめぐるネオ55年体制?
政治学者の境家史郎は、現在の日本政治に根強く残る「外交安全保障・憲法」の軸を強調し、安倍政権の下であらためて「戦後民主主義か軍国主義か」による対立軸が引かれたとして、それを「ネオ55年体制」と名づけている。
もちろん、55年体制が崩壊した後も、一気に「旧革新」を支えた支持層や争点がなくなったわけではない。憲法や安全保障問題は、「歴史的慣性(inertia)」と経路依存性によって、その後も政治的対立軸としての力を失っていない。
また、第二次安倍政権は、新自由主義「改革」よりも憲法改正や集団的自衛権を前面に出して取り組み、野党もまたそれに抵抗する布陣の再編成を迫られた。2015年の安保法制反対運動は1960年安保に比較される政治運動であり、待鳥聡史にいわせれば、2015年安保で「社会党的なるものを支持する人たち」が「再発見」されたことが、立憲民主党の結成と台頭に繋がったという。
しかし、1960年安保と2015年安保は、運動の動員規模でも、「革新」を支えた中間団体の組織力という意味でも、まったく異なるものである。60年安保では、国会前のデモだけでなく、労働組合の後方支援が全国規模で展開され、それが「革新」陣営を支える分厚い支持基盤へと連なった。
他方、2015年安保では、SEALDsのメンバーは500人ほどで、実際は団塊の世代の高齢者が支えた。大学という拠点も労働組合という組織もなかった。「安保法制のデモは『前方展開』のみで行われ、社会の組織化にはつながらなかった」、それゆえ「2010年代の社会運動が、そのまま旧来型の革新政治の基盤になることはない」という木下ちがやの指摘は妥当であろう。
また、2025年には「団塊の世代」が後期高齢者となり、有権者の中心的ボリュームは大きく若年世代へ移行する。戦争体験の記憶はますます風化し、その肌感覚に基づいた「外交安全保障・憲法」の争点軸も、相対的に後景に退くであろう。
人口減少と「行財政改革・成長」の争点
日本政治を中長期的に規定するであろう最大の課題は少子高齢化と人口減少であり、その大枠の下で、今後、「行財政改革・成長」の対立軸が相対的により前面に出てくることが予想される。
「行財政改革・成長」の対立軸は、市場競争の強者である大企業と、競争力は弱いが組織力によって政治的影響力を持つ再分配依存セクター(農業団体、中小自営業の団体、福祉関連団体)などに立脚しており、「現実の社会集団間の利害対立に根差しているという点においても非常に大きな意味」を持つ(平野浩)。
しかし、その対立軸が前面に出てきた場合、政党はどのような形で対立軸に順応するか、依然として混迷している。「外交安全保障・憲法」の軸で与野党対立が引かれ続ければそれは「薄められた保革対立」になろうが、「行財政改革・成長」の軸で引かれ直されれば、エリートレベルと有権者レベルの双方での本格的な「政界再編」へと繋がる可能性が高い。
立憲野党における「改革」と「旧革新」の提携
ここにあって、立憲民主党はじめ野党も、大きな自己変革を迫られている。民主党系政党は、これまで、中道改革層とリベラル左派層との、相反する(とされる)二つの方向性に挟まれ、カニのように横一線に右往左往を繰り返してきた。
しかし、民主党系政党は、「左にぶれると中道を失うぞ/保守層を狙えばリベラルな支持者を失うぞ」式の発想から、いい加減、脱却する時ではないだろうか。むしろその二つを弁証法的に統合し、一貫した視点から包含した理念と政策パッケージを示す必要がある。
私は『中央公論』の論文「1993年体制と『3・2・1の法則』」において、「リベラル(旧革新)」と「改革」との結合を唱えた。すなわち、現下の「3・2・1」の力関係を前提とすれば、単純に考えて、「リベラル(旧革新)」と「改革」を結合させる「2+1=3」のアプローチである。
もとよりこれは、立憲と維新との政党合流を意味するものでは毛頭なく、立憲が「改革」型のアジェンダを包摂していくことである。平成年間、「改革」は確実に有権者の支持を集め、市民社会の「同意」を獲得してきた。少子高齢化を与件とすれば、公共インフラの整理統合や自治体議員の定数見直し、規制緩和による生活向上の実感など、時代の変化にあわせた行政の役割の再定義は避けて通れない。野党には、政府の役割のうち何を大きくし何を小さくすべきかをめぐる、明確で一貫した基準を打ち立てることが求められる。
政治学者の吉田徹の言葉でこれを換言すれば、「新自由主義の極」と「社会民主主義の極」との統合ということもできる。吉田によれば、ポスト55年体制期にあって、野党勢力は再分配を重視する「社会民主主義の極」と制度改革に比重をおく「新自由主義の極」という二つの極に切り裂かれてきた。
「再分配と改革という二つの極は、政策的には相互補完的でありながら、体系的な理念としてみた場合、相反することになる」が、「小選挙区制を前提とすれば、この両極の結集ないし協力関係が不可欠となる」(吉田徹)。
「社会民主主義」と「新自由主義」の両極の結集とは、単に双方の足し合わせに終わるものであってはならない。時代の変化にあわせて、政府機能のどこを拡充し、どこをスリム化するか、その判断を社会的弱者の立場から一貫した基準で行うことである。大きくすべきは大きく、小さくすべきは小さく、時代にあわせて政府の役割を再定義する仕事である。
日本政治は今、筋書きのない流動期に足を踏み入れている。われわれの未来史は、過去に捉われた思考停止を拒否し、流動する現実を誠実に見つめ、新しい時代を掴もうとする意識の先に描かれるだろう。