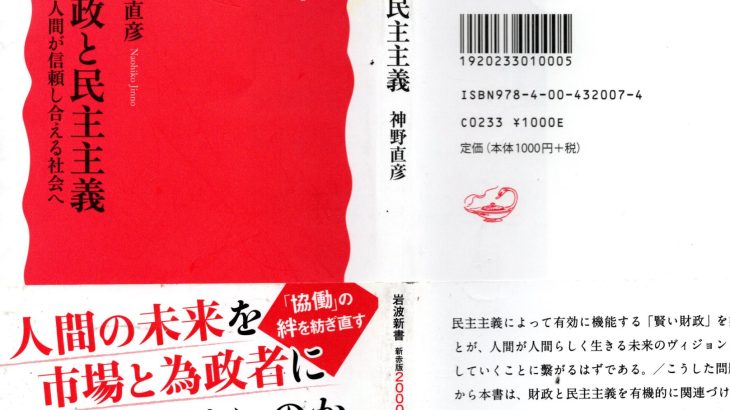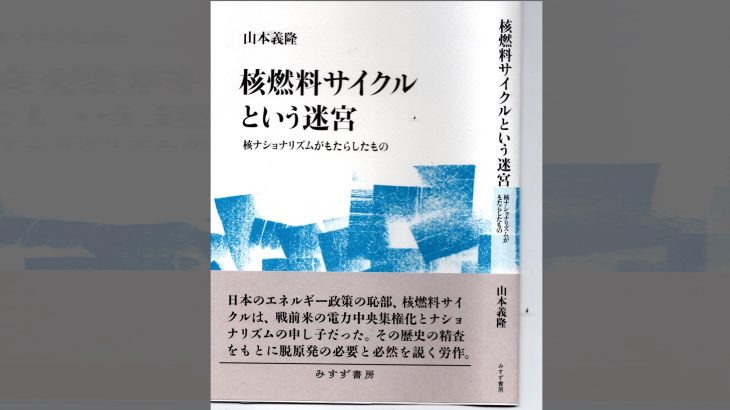白川真澄
岸田政権は、内閣支持率の低迷から抜け出せないでいる。9月の内閣改造も、ほとんど支持率回復に効果がなかった。そこで、大型の経済対策(巨額の補正予算)を打ち出して挽回を図り、解散・総選挙の機会を窺おうとしている。経済対策の柱になるのが、3%超えインフレが1年間も続いているなかでの物価対策である。具体的には、電気・ガス料金の軽減策と並んで、ガソリン価格を安く抑えるための補助金を年末まで継続する。これに対して、野党もこぞってガソリン税の引き下げ(あるいはガソリン税ゼロ)を要求している。
ガソリン価格を政策的に抑制することは、石油元売り会社への補助金の給付であれガソリン税の引き下げであれ、脱炭素化に逆行する愚行だ。しかも、有害無益な金融緩和政策が招いている円安による価格高騰を無視した的外れな政策でもある。
異常気象が「ニューノーマル」に、それでもCO2排出削減は進んでいない
今年の夏の暑さは異常だった。人間の体温を超える気温が全国各地で出現し、お盆を過ぎても猛暑日に見舞われた。7月と8月の日本の平均気温は、観測史上最も高くなった。世界の平均気温も7月には過去最高となり、高温や熱波が世界各地を襲った。ハワイ・マウイ島の火災では100人以上もの死者が出たが、世界の山火事で焼失した面積は年800万ha以上と、20年前の2倍にもなる(1)。「地球沸騰化の時代」(グテーレス国連事務総長)が到来し、異常気象が「ニューノーマル」(WHO)になっている。
にもかかわらず、温暖化防止のためのCO2排出削減は、遅々として進んでいない。1.5度目標(地球の平均気温の上昇を産業革命期から1.5度以内に抑える)の達成には2030年までにCO2排出量を半減する、そのために年7.6%削減することが必要とされる。しかし、2020年にはコロナ・パンデミックによる経済危機(GDPが-3.1%)によって5.8%減ったが、経済が回復した21年(GDPが+6.1%)には6.0%も急増した。22年も0.9%増え、年368億㌧と過去最大になった。このままでは、1.5度目標の達成はとうてい望めない。
世界的には再生可能エネルギーの導入も進んでいるが、同時にCO2を大量に排出する石炭火力発電も目立って増えている。21年の石炭火力発電量は、世界で前年比9%増の10兆422億kw時と過去最大になった(2)。とくに、日本では発電に占める石炭火力の割合は31.0%(21年)と、再エネの20.2%を大きく上回っている(ドイツは再エネの割合が22年に48.5%)。日本は、昨年秋のCOP27の場でも石炭火力の縮小・廃止に激しく抵抗し、全化石燃料の段階的廃止の合意形成の足を引っ張った。
岸田政権は、GX(グリーントランスフォーメーション)の推進を謳って、再エネの割合の拡大(2030年で22~24%)を目標に掲げている。しかし、実際には再エネの拡大よりも、むしろ40年超えの老朽原発3基を含めた原発再稼働(全国33基中11基)に熱中している。
※注1:朝日新聞23年9月17日
注2:日経新聞22年6月4日
ガソリン価格を安く抑える巨額の補助金支出
脱炭素化に逆行する動きのなかで見過ごせないのが、化石燃料、とくにガソリンに対する各国政府の巨額の補助金支出である。原油価格は、産油国が脱炭素化の流れを見越して供給制限を行なったために上昇傾向に転じ、2021年以降の世界的なインフレを招いた。さらに、22年2月のウクライナ戦争の勃発がこれを加速した。
ガソリン価格が急騰したことに対して、各国政府はいっせいに価格を安く抑える政策を導入した。ドイツとイギリスは、エネルギー税あるいは燃料税を一定期間引き下げる措置をとった。フランスは、ガソリンの店頭価格の割引を実施した(割引分を政府が払い戻す)。日本では、22年1月から石油元売り会社に対して補助金を給付することでガソリン価格を168円以下に抑える措置が導入された[図1]

IMFによれば、ガソリンなど化石燃料に対する直接の補助金だけで年約1兆3000億ドル(約185兆円)、ガソリン税の減税など「間接的な補助金」を合わせると約7兆ドル(約1000兆円)に達する(2022年)。その金額は、世界のGDPの7.1%にもなり、教育支出4.3%をはるかに上回る巨額な規模になる(3)。
ガソリン価格の上昇は、家計を圧迫する反面、ガソリンへの需要、つまりクルマの運転を控えさせ、CO2排出を減らす作用として働く。しかし、ガソリンへの補助金支出による価格引き下げはクルマの使用を増やして、CO2排出削減にブレーキをかける。脱炭素化に逆行する政策である。
そのため、ドイツはエネルギー税の引き下げを3か月間で終了し、フランスはガソリンの割引制度を22年末で終えた(23年初めの3カ月は低所得者に対象を絞って支援)。イギリスだけは高インフレが収まらないことから、燃料税の引き下げ措置を24年3月まで延長することを決めた。
日本では、どうか。石油元売り会社への補助金給付はすでに4兆円を超え、9月末に打ち切られることになっていた。ところが、8月末にガソリンの店頭価格が1リットルあたり185.6円と、2008年8月以来15年ぶりの最高値を更新した。そこで、岸田政権は、ガソリン価格を175円程度に抑えるように補助金の支給を年末まで続ける方針を決定したのである。追加の財政支出は1.2兆円と見込まれる。
※注3:日経新聞23年9月21日
日本政府はガソリンの消費を下支えして、CO2排出量を増やす
もともと、日本のガソリン価格は、ドイツなどに比べて格段に低い。ドイツの1リットルあたり1.73ドルに対して1.34ドル(21年2月)と、3割近く安い。本体価格はほぼ同じだから、この価格差はガソリン税の差から来ている(日本0.66ドル、ドイツ1.07ドル)。
ガソリン価格の国際比較(2021年2月)
本体価格 税額 合計
日本 0.68 0.66 1.34
米国 0.53 0.13 0.66
英国 0.59 1.08 1.67
フランス 0.62 1.13 1.74
ドイツ 0.66 1.07 1.73
単位:米ドル/1リットル
(資源エネルギー庁「エネルギー白書」2021)
日本はこれまで、ガソリン税(あるいは炭素税)を引き上げて価格を高めに誘導することによって、ガソリンの需要を減らしてCO2排出量を削減する政策を積極的に採ってこなかったのだ。そして、2022年1月からは、石油元売り会社に巨額の補助金を支給してガソリン価格の高騰を抑えてきた。その結果、2022年度の国内のガソリン販売量は、本来なら価格高騰で一気に減るはずなのに、むしろ僅かだが前年度よりも増えている(445万㎘ → 448㎘)(4)。この7月で見ると、2人以上世帯のガソリン消費は、2年前に比べて7.2%も増えている(5)。
さらに、ガソリンへの補助金支給を年末まで延長することを決めたのである。ドイツがエネルギー税の引き下げ措置を22年中に終えたのとは対照的である。岸田政権はガソリン車に乗ることを奨励し、露骨にCO2排出削減に背を向けているとしか言いようがない。立憲民主党も、補助金ではなくガソリン税の引き下げ(トリガー条項の発動)を要求している。れいわに至っては、ガソリン税ゼロを主張している。政権と五十歩百歩だ。
※注4:経産省 石油統計
注5:日経新聞23年9月13日
円安を止めなけば、ガソリン価格の高騰はいつまでも続く
ガソリンへの補助金継続は、脱炭素化に逆行するだけではない。物価対策としても的外れなのである。というのは、2022年初頭からこの夏までのガソリン価格の上昇は、補助金によって原油価格の値上がり分(1㍑11.0円)を相殺しても19円となるが、その84%、16円分は急激な円安によるからである(6)。
円の対ドル相場は、22年1月の1㌦=114円から今年8月の144円(9月は148円)へと急落してきた。これは、日本の国際競争力の低下(貿易収支の赤字拡大)が根底にあるが、直接には日米間の金利差の拡大から来ている。米国がインフレ抑制のために政策金利を5%にまで引き上げてきたのに対して、日本は3%を超えるインフレの進行にもかかわらず金融緩和、すなわちゼロ金利政策を頑なに続けている。1000兆円を超える政府債務を抱えてしまった現在、金利引き上げ(金融正常化)は国債の利払いを急増させるから、やりたくても簡単にはやれない。身動きできない状態に陥っているのだ。
輸入に全面的に頼る食料の値上がりも含めて、急激な円安がインフレをもたらしている。円安を止めなければ、ガソリン価格の高騰も収まらず、それに応じて補助金支出がズルズルと続けられ、年を超えても繰り返されることになる。必要なことは、金融緩和政策をすみやかに転換して正常化し、円安に歯止めをかけることである。円安を放置したままガソリン価格の上昇に引きずられて補助金を出し続ける政策は、終わりが見通せない的外れなものである。
※注6:日経23年8月31日
真っ当な物価対策――低所得層と地方の居住者に支援を
インフレは、平等主義ではない。消費者物価上昇率は所得の低い階層ほど高く、所得の高い層ほど低くなっている(22年5月では勤労者世帯で上昇率2.2%だが、最も所得の低い階層では2.5%、最も所得の高い階層では2.1%)。低所得世帯では、値上がりの大きい食料やエネルギー(電気・ガス)の消費に占める割合が大きいからである。そのため、低所得世帯は生活防衛のために消費支出を大きく減らすことを強いられているが、高所得世帯の消費支出はインフレのなかでも増え続けている[図2]。

また、地方の居住者は、鉄道や路線バスの廃止が相次ぎ、ますますクルマに頼るしかなくなっている。そのため、人口5万人未満の市町村では、2人以上世帯のガソリン消費は2年前より26.1%も増えている。価格抑制策があるとはいえ、ガソリン支出の負担が重くのしかかっている。
したがって、求められる物価対策の第一は、最も打撃を受けている低所得層および地方居住者を支援する、すなわち「物価手当」を支給することである。住民税非課税世帯が3,000万(~1600万)世帯、人口5万人以下の市町村の世帯が800万世帯とすると、一律10万円を1回給付しても3.8兆円である(ただし、世帯単位ではなく個人単位の給付にすべきである)。石油元売り会社へのガソリン補助金よりは少ない金額で済む。
岸田政権も、物価対策として低所得層への給付金支給を行なったが(一律3万円、23年3月)、新たに追加の支給を経済対策に盛り込む検討を始めたと報じられている。それならば、脱炭素化に逆行するガソリン補助金をきっぱり止めて、十分な物価手当を支給するべきである。また、ガソリン税は引き下げずに炭素税に組み替えて、CO2排出1㌧あたり289円という極端に低い現在の炭素税(地球温暖化対策税)を5,000~10,000円に引き上げる方向に進まなければならない。
公共交通機関の料金引き下げと拡充で脱クルマ社会へ
第二に、鉄道や電車など公共交通機関の利用を促進するために運賃を値下げすることである。ガソリン価格が高騰しクルマに乗るコストが高くつくのだから、鉄道や電車の運賃を下げてその利用を促進することは、生活防衛策にもなるし脱炭素化の後押しにもなる。1人を1㎞運ぶときに排出されるCO2は、自家用車が130gであるのに対して鉄道は17ℊにとどまる(2019年)。バスでも57ℊと、半分以下で済む(7)。
興味深いことに、物価対策として、ドイツではマイカーではなく鉄道や地下鉄や路面電車やバスを使用する場合には乗り放題の定額チケットを提供した(3か月間有効)。イギリスも鉄道料金を期限付きで半額にするチケットを販売したし、米国ではカリフォルニア州の公共交通機関の利用は3カ月間無料にされた。
ところが、日本では正反対の動きがまかり通っている。JRや私鉄や地下鉄が、利用客の減少による減収を口実にして今年3月からいっせいに運賃値上げを行なったのである。公共交通機関の利用を控えさせる措置でしかない。公共交通機関の運賃を、インフレの高進している期間中はむろんのこと将来的にも引き下げる政策をとるべきである。そのためには税の投入も必要になる。
また、ローカル線を廃止する計画も、ただちに中止するべきだ。クルマ社会に代わって、地方では鉄道や路線バスを復活し、コミュニティバスを普及する。都市ではマイカーの中心部への乗り入れを禁止し、路面電車を導入する(宇都宮市のLRTが先行例)といった戦略に転換しなければならない。
政治の世界では脱炭素化に逆行する政策だけが叫ばれているが(自公政権はガソリンへの補助金、野党はガソリン税の引き下げ)、次のような提案のほうがずっと真っ当である。
「G7でガソリン補助金を継続しているのは日本と英国だけです。今後は燃料高の影響が大きい低所得世帯や零細企業、公共交通機関などに的を絞った支援も検討する必要があるかもしれません」(8)。
第三に、より長期の視野に立てば、エネルギーと食料の大部分を輸入に頼っている経済構造を変革しなければならない。日本のエネルギーの自給率は13%、食料自給率は38%(いずれも22年)にすぎない。
ここ数年、世界的なエネルギーと食料の供給はひっ迫し不安定化している。輸入されるエネルギーや食料の価格は、これからますます高くなることが予想される。《自動車の輸出で貿易黒字を稼ぎ、エネルギーと食料を欲しいだけ安く買う》という従来の仕組みは、もはや成り立たなくなっているのだ。軍事と結びついた「食料安全保障」「エネルギー安全保障」といった枠組みを突破しながら、地域におけるエネルギーと食の自給の実現に向かって本格的に踏みださなければならない。
※注7:国交省「モーダルシフトとは」
注8:日経新聞23年9月23日「マネーのまなび」
《参考》
白川真澄「岸田政権と野党の物価高対策を斬る/ガソリン価格抑制のための補助金もガソリン税減税も愚策だ!」(PP研WEB2022年6月10日)
(2023年10月3日記)