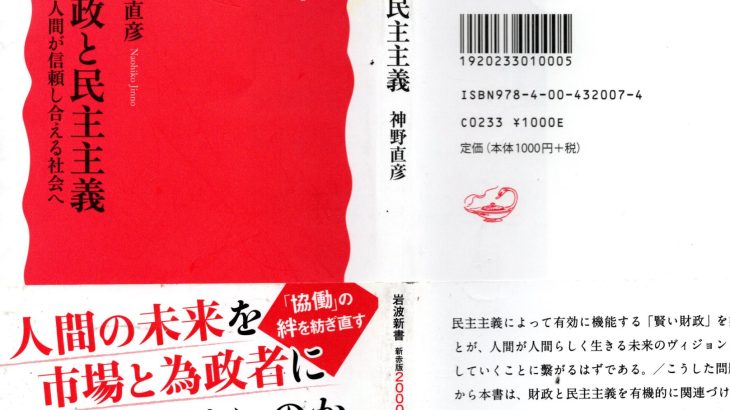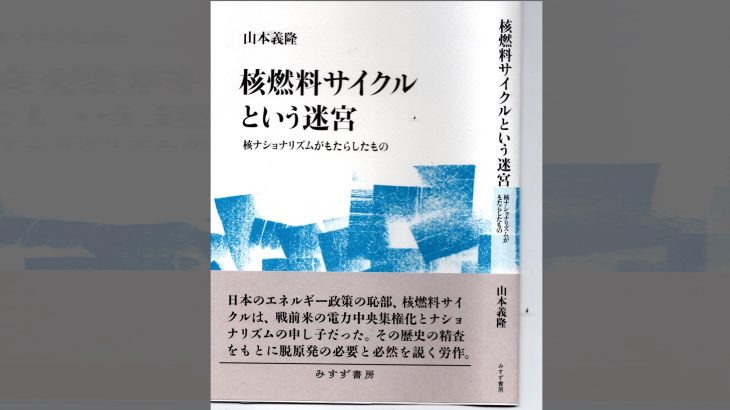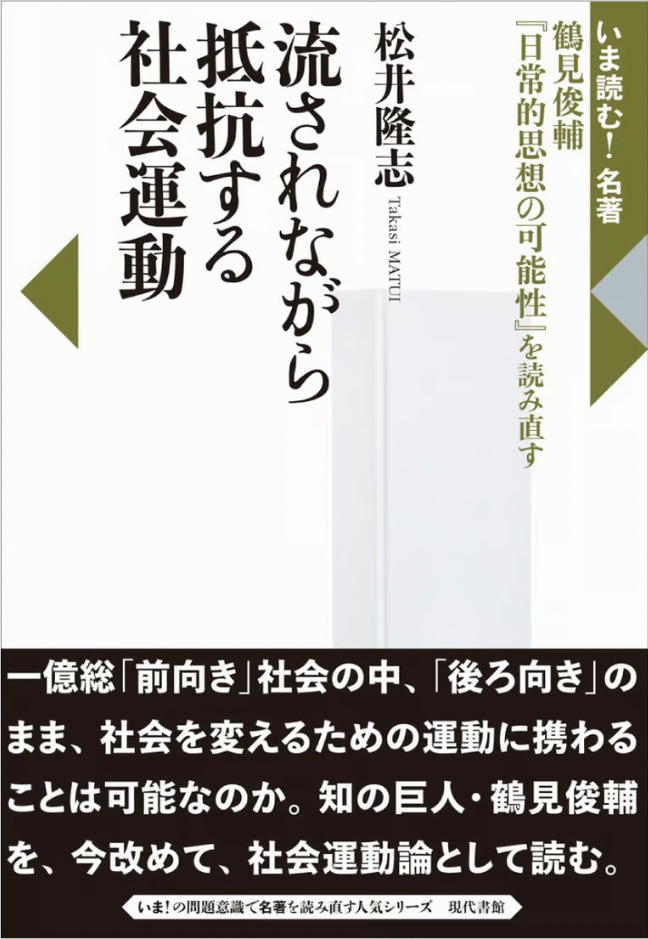
対象書籍:松井隆志『流されながら抵抗する社会運動―鶴見俊輔『日常的思想の可能性』を読み直す』(現代書館、2024年)
安藤丈将(大学教員)
近年、鶴見俊輔の著作の再読が進んでいる。歴史、哲学、社会学など異なる分野の研究者、ジャーナリストなどが鶴見に興味を示し、静かなブームともいえる状況が続いている。松井隆志『流されながら抵抗する社会運動』も、鶴見の思想を扱っている。筆者は、本書の特徴を、鶴見の思想を「一つの社会運動論として受け取り、展開し、その有効性を論じ」(18頁)るという。
ここで「社会運動論として受け取」るという言葉の意味には解説を要するだろう。まず、それは、社会運動史の文脈に位置づけることを指している。そのために筆者は、鶴見がもっとも深く運動団体(グループ)に関わっていた1960年代に焦点を絞っている。この時期の彼は、声なき声の会、ベ平連、非暴力反戦行動委員会、脱走兵援助活動に関わっており、その関わりの中で生まれた『日常的思想の可能性』(1967年刊行)を読み解いている。
しかし、本書を読んでみると、「社会運動論として受け取」るということの含意は、どうもそれだけではなさそうである。先に結論を述べると、私は、市民の自己統治の技術を言語化した思想家として鶴見を読む試み、と理解している。説明を加えてみよう。社会運動について勉強したことのある人が「社会運動論」と聞いた時に念頭に浮かべるのは、社会学の社会運動論であろう。そこでは、一方になぜその運動が成功、失敗するのかを研究する動員論と呼ばれる潮流が、他方にその運動には何の意義、意味があるのかを研究する行為論と呼ばれる潮流がある(この点に関しては、濱西栄司ほか『問いからはじめる社会運動論』有斐閣、2020年、が参考になる)。
これ以外に、知識人の社会運動論を思い浮かべる人もいるかもしれない。それは、最先端の学術的知見をもとに、社会状況や社会問題を分析し、運動の進むべき道を示すような知的活動である。これはかつての啓蒙的知識人(丸山真男など)の「夜店」活動に始まり、今日もメディア等で見かけることができる。
本書が鶴見を通して描こうとする運動論は、これらとは異なる次元にある。それがもっとも明確に表れているのは、第2章に出てくる彼の集団論である。そのキーワードを挙げていくと、まず、「つつみこみ学風」(89頁)である。グループの話し合いの際に、主題を緩く設定しておき、参加者を広く包摂し、偶然のきっかけで生まれるアイディアに開かれたり、集団的思考を内発的に発展させたりする。次に、「研鑽会」(93頁)である。グループで合宿のような共同生活の機会を設け、日常の経験と言葉で語り合うことで、合意形成をスムーズにする。さらに、「反射」(107頁)である。一人ひとりが異論を発する練習の機会を日常的に設けて、権力者からの、あるいは集団内の同調圧力に屈しないような身体性を身に付ける。
これらは、市民の政治技術とも呼べるものである。ここで「政治」とは、政治家との交渉や選挙活動の場で必要とされる技術を指しているわけではない。そうではなく、人びとが集団(グループ)に参加する時に、他者を尊重しながら意見を交換し、合意をつくり出して行動につなげ、その行動の輪を広げて影響力を拡大し、ひいては社会変革に結びつける時の技術である。社会運動のための技術と言い換えることもできる(ちなみに筆者は、「社会運動のため知恵」(94頁)という言葉を使っている)。以上のような意味で、私は、本書が市民の政治技術論として鶴見思想を提示する本であると見ている。
社会学や知識人の社会運動論とは違うが、本書に類似する研究領域がないこともない。私が本書を読みながら頭に浮かんだのは、コミュニティ・オーガナイジング論である(比較的最近出版されたものでいえば、ブラック・ライブズ・マター運動で知られたアリシア・ガーザ『世界を動かす変革の力』明石書店、2021年、を挙げられる)。これは、主にアメリカのアクティヴィストが地域住民を組織する方法に関して運動の中で蓄積されてきた技術を言語化したものであり、本書とも共通する点が多い。社会学の社会運動論や知識人の運動論の対象とは必ずしも重なっておらず、日本では研究上の空白になっている領域でもある。このように本書は、鶴見を再読しながら、社会運動との相互作用の中で形成される実践知を形にしようとした本であるといえる。
既述のように、本書は鶴見が運動グループに深く関わっていた1960年代に焦点を当てて彼の思索を読み解いている。これによって、鶴見思想を市民の政治技術論として読み直すことが可能になったが、他方、私は、政治技術論の「その後」がどうであったのかという疑問を抱いた。実は著者本人もこの問題関心を持っている。松井は、『戦後思想の再審判』(法律文化社、2015年)に所収された鶴見に関する論文の中で、高度成長期以降の鶴見思想を検討し、それが「人生訓」に近づいていったという興味深い指摘をしている。すなわち、社会変革のための技術という側面が薄くなり、個人化された生存の技術という側面が色濃くなっているというのだ。
技術は常に「運動の技術」になるわけではなく、その他の活動の局面においても応用することができる。たとえば、「つつみこみ学風」や「研鑽会」は、企業で多様な背景の社員の発言を促し、彼らの団結心を高め、生産性を向上するためにも利用可能であろう。技術は、それと結びつく社会的文脈によって異なる機能を果たす。
この点でいえば、本書では、政治技術論の「その後」という問題関心は後景に退いている。筆者は、「後史」をあえて軽視するという個所で(61頁)、こうした疑問に対して布石を打っているように見える。議論の範囲の設定という意味では理解できなくもないが、「後史」も含めて初めて鶴見思想を全体として評価できるのではないかという疑問は消えなかった。鶴見思想の「その後」を検討する時には、彼を取り巻く社会の変化との相互作用を目配りしなくてはならないので、彼の生きた期間を考えると膨大な作業になるであろう。このような市民の政治技術論として鶴見思想を蘇らせる試みは、運動の実践知を求める多くの読者の興味をひくものであることは間違いない。